走行中に突然、オレンジ色のエンジン警告灯が点滅し、車体がガタガタと揺れると本当に不安になりますよね。
このエンジン警告灯の点滅とガタガタする現象の根本的な原因は何なのか、
チカチカするのは故障のサインなのか、
また点灯と点滅の違いは何か、
多くの方が疑問に思うはずです。
時にはスピードが出ない、ガタガタという振動と同時に焦げ臭いにおいがするなど、深刻な状況も考えられます。
点灯するのはノッキングが原因という話や、点滅した後に消えた場合の対処法、さらには修理にかかる費用についても気になるところです。
特にホンダやダイハツの車でこの症状が出た場合、どうすれば良いのでしょうか。
この記事では、これらの多くの疑問に対し、詳しく解説していきます。
- エンジン警告灯が点滅・ガタガタする原因がわかる
- 症状別の具体的な対処法を正しく理解できる
- 修理にかかる費用の目安を把握できる
- 警告灯を放置するリスクと事前の対策がわかる
エンジン警告灯が点滅しガタガタする主な原因と症状
- エンジン警告灯が点滅しガタガタする原因
- エンジン警告灯の点滅と点灯の違いとは
- オレンジ色のエンジン警告灯が点滅する意味
- チカチカするのは重大な故障のサイン?
- 点灯するのはノッキングが原因の場合も
- スピードが出ない症状は特に危険
- ガタガタと焦げ臭いにおいが伴う場合
エンジン警告灯が点滅しガタガタする原因

エンジン警告灯が点滅し、車体がガタガタと振動する場合、その最も一般的な原因は「エンジンの失火(ミスファイア)」です。
失火とは、エンジンのシリンダー内でガソリンと空気の混合気が正常に爆発(燃焼)していない状態を指します。
車は複数のシリンダー(一般的に軽自動車で3気筒、普通車で4気筒以上)が連携して動いていますが、そのうちの1つでも正常に機能しないと、エンジンの回転バランスが崩れてしまいます。これが、ガタガタという不快な振動の正体です。
この失火を引き起こす具体的な原因は、主に以下の3つの系統に分類されます。
失火を引き起こす主な要因
- 点火系のトラブル:エンジン内で混合気に火花を飛ばす部品の故障です。
- 燃料供給系のトラブル:エンジンに適切な量の燃料を送れなくなる不具合です。
- 吸排気系・センサー系のトラブル:空気の量を調整したり、エンジンの状態を監視したりする部品の異常です。
例えば、点火系では「イグニッションコイル」や「スパークプラグ」といった部品が劣化すると、正常な火花が飛ばなくなり失火につながります。これらは消耗品であり、走行距離が増えるにつれて交換が必要になる部品です。
燃料供給系では、燃料をエンジンに噴射する「インジェクター」の詰まりや、燃料をタンクから圧送する「燃料ポンプ」の故障が考えられます。
また、最近の車は非常に多くのセンサーで制御されており、「O2センサー」や「エアフローセンサー」などが故障すると、コンピューターが燃焼状態を正しく制御できなくなり、結果として失火を招くことがあるのです。
エンジン警告灯の点滅と点灯の違いとは
エンジン警告灯には、「点灯」し続ける状態と、「点滅」する状態の2種類があり、それぞれ意味合いが異なります。
結論から言うと、点滅している方がはるかに緊急性が高く、危険な状態を示しています。
「点灯」は、エンジン制御システム(ECU)が何らかの異常を検知し、そのエラーコードを記録したことを示します。
異常は過去に一度起きただけかもしれませんし、現在も継続中かもしれませんが、必ずしも走行に即時的な危険が伴うわけではありません。例えば、センサーの一時的なエラーでも点灯することがあります。
一方、「点滅」は、現在進行形でエンジンに深刻なダメージを与えかねない、重大なトラブルが発生していることを示唆しています。
特に、前述した「失火」を検知した場合に点滅することが多いです。
失火状態のまま走行を続けると、未燃焼のガソリンが排気管に流れ込み、高価な部品である「触媒コンバーター」を過熱させて損傷させる可能性があります。
このため、コンピューターはドライバーに最大限の警告を送るために、警告灯を点滅させるのです。
| 状態 | 緊急度 | 主な意味 | 対処法 |
|---|---|---|---|
| 点灯 | 中 | エンジンシステムが異常を記録した状態。即時走行不能とは限らない。 | なるべく早く整備工場で点検を受ける。 |
| 点滅 | 高(危険) | エンジンに深刻なダメージを与えうる異常が現在進行中である状態。(特に失火が多い) | 直ちに安全な場所に停車し、運転を中止する。 |
オレンジ色のエンジン警告灯が点滅する意味

車のメーターパネルに表示される警告灯の色は、国際規格(ISO)によって意味が定められており、世界中の車で共通しています。
色は主に「緑」「オレンジ(黄)」「赤」の3種類で、信号機のように直感的に危険度を理解できるようになっています。
警告灯の色の意味
- 緑色:安全。システムの作動状態を示します。(例:方向指示器、ECOモードなど)
- オレンジ色(黄色):注意。緊急停車は不要なものの、速やかな点検が必要な状態です。
- 赤色:危険。直ちに運転を中止し、安全を確保する必要がある深刻な異常です。(例:油圧警告灯、水温警告灯など)
エンジン警告灯は、このうち「オレンジ色」に分類されます。
つまり、「直ちに車を停めなければならない」という赤色警告ほどの緊急性はないものの、「異常が発生しているので、できるだけ早く専門家による点検を受けてください」という注意喚起のサインです。
ただし、これはあくまで「点灯」の場合です。
前述の通り、同じオレンジ色でも「点滅」している場合は、赤色警告に匹敵する、あるいはそれ以上に危険な状況だと認識する必要があります。
エンジン本体や関連部品に回復不可能なダメージが及ぶ前に、速やかに対処することが重要です。
チカチカするのは重大な故障のサイン?

エンジン警告灯がチカチカと点滅するのは、重大な故障が発生している可能性が極めて高いサインと捉えるべきです。
この点滅は、単なる警告を超えて「このままでは車が壊れますよ」というECU(エンジン・コントロール・ユニット)からの悲鳴に近いものです。
「チカチカするだけ」と軽く考え、走行を続けるのは絶対に避けてください。
目に見える症状がガタガタという振動だけでも、エンジン内部や排気システムでは深刻な問題が進行している可能性があります。
最も懸念されるのが、失火によって未燃焼ガスがマフラー内部にある触媒コンバーター(キャタライザー)に流れ込むことです。
触媒は、排気ガス中の有害物質を無害化するための装置で、内部は白金やパラジウムといった貴金属でできており、非常に高温になります。
ここに可燃性の高い未燃焼ガスが流れ込むと、触媒内部で異常燃焼が起こり、1000℃を超えるような異常な高温に達してしまいます。
結果として、触媒が溶けたり、詰まったりして、排気効率が極端に悪化します。
こうなると、エンジン本来のパワーが出なくなるだけでなく、数十万円という高額な修理費用がかかることにもなりかねません。
点滅を無視するリスク
- 触媒コンバーターの損傷(修理費用:10万円~)
- エンジン内部の損傷(ピストンやシリンダーの傷)
- 燃費の大幅な悪化
- 最終的にエンジンが始動しなくなる
このように、チカチカという点滅は、より高額な修理費用につながる二次被害を防ぐための最後の警告なのです。
点灯するのはノッキングが原因の場合も

エンジン警告灯が点灯する原因の一つとして、「ノッキング」が関係している場合があります。
ノッキングとは、エンジン内部で意図しないタイミングで異常な燃焼が起こり、「カリカリ」「キンキン」といった金属を叩くような異音が発生する現象です。
本来、エンジンはスパークプラグが火花を飛ばしたタイミングで、燃焼がシリンダー全体にきれいに広がっていきます。
しかし、何らかの原因でプラグが点火する前に混合気が自然発火してしまうと、衝撃波が発生し、エンジンにダメージを与えてしまうのです。
この異常な振動を「ノックセンサー」が検知すると、ECUはエンジンを保護するために点火タイミングを遅らせるなどの制御を行います。
そして、この制御が頻繁に行われたり、制御の限界を超えたりした場合に、異常として記録されエンジン警告灯が点灯することがあります。
ノッキングの主な原因
- 粗悪なガソリンの使用:オクタン価の低いガソリンは、自然発火しやすい性質があります。
- エンジン内部のカーボン堆積:燃焼室に溜まったススが高温になり、火種となって異常燃焼を引き起こします。
- エンジンの過熱(オーバーヒート):エンジン自体の温度が高すぎると、混合気が発火しやすくなります。
ノッキングが原因で警告灯が点灯した場合、ガタガタという振動よりも「カリカリ」という異音が主な症状として現れることが多いです。
しかし、放置すればエンジン内部のピストンなどを損傷させる重大なトラブルにつながるため、こちらも速やかな点検が必要になります。
スピードが出ない症状は特に危険
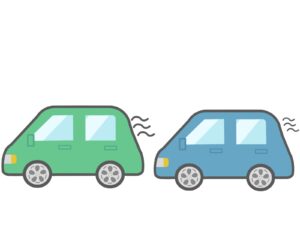
エンジン警告灯の点滅とガタガタという振動に加えて、「アクセルを踏んでもスピードが出ない」「加速が極端に鈍い」という症状が伴う場合、それは非常に危険な状態です。
これは、車のECUがエンジンやトランスミッションを保護するために、意図的に出力を制限する「セーフモード(リンプホームモード)」に移行している可能性が高いです。
セーフモードは、車が「これ以上の走行は危険」と自己判断した際に作動する緊急機能です。
エンジン回転数や車速の上限を強制的に低く抑えることで、ドライバーに異常を知らせると同時に、ダメージの拡大を防ぎ、なんとか最寄りの安全な場所や整備工場までたどり着けるようにすることを目的としています。
セーフモードの主な症状
- アクセルを踏んでも、エンジンの回転数が上がらない(例:3000回転以上にならない)。
- スピードが一定以上出ない(例:時速40~60kmが上限になる)。
- オートマチックトランスミッションのギアが特定の段数(例:2速や3速)に固定される。
- アイドリングが不安定になる。
この状態で高速道路などを走行するのは極めて危険です。
周囲の車の流れに乗れず、追突事故を誘発する恐れがあります。
もし走行中にこの症状が発生したら、直ちにハザードランプを点灯させて後続車に異常を知らせ、速やかに路肩やサービスエリアなどの安全な場所に車を停止させてください。
自走して整備工場に向かうのは避け、レッカーサービスを利用することを強く推奨します。
ガタガタと焦げ臭いにおいが伴う場合
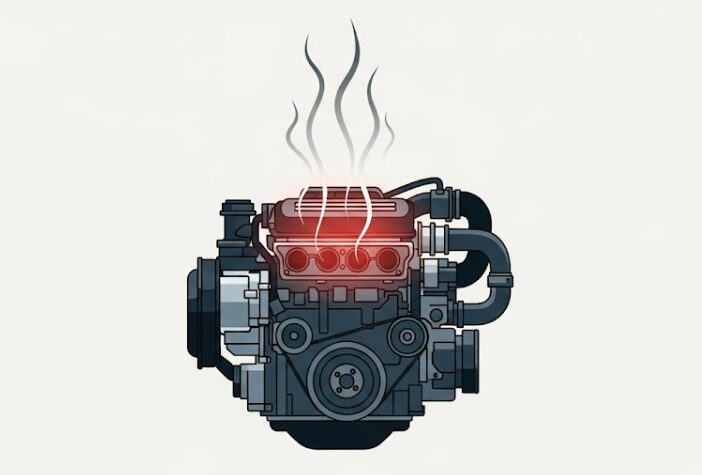
エンジンからのガタガタという振動と共に、「何か焦げ臭いにおい」が車内や車外で感じられた場合、これは最も警戒すべきサインの一つです。
火災につながる危険性も否定できないため、いかなる理由があっても走行を続けず、即座に安全な場所に停車し、エンジンを停止してください。
焦げ臭いにおいの原因はいくつか考えられますが、振動と同時に発生している場合、以下のような深刻なトラブルが疑われます。
- エンジンオイルの漏れ:エンジンのヘッドカバーなどから漏れたオイルが、高温になっている排気管(エキゾーストマニホールドなど)に付着して焼けると、独特の焦げ臭いにおいが発生します。オイル不足はエンジンの焼き付きにつながります。
- 電気系統のショート:振動によって劣化した配線の被膜が破れ、ショート(短絡)を起こしている可能性があります。ビニールが焼けるようなにおいが特徴で、車両火災の直接的な原因となり非常に危険です。
- ベルト類の滑りや焼き付き:ファンベルトなどのゴム部品が劣化して滑ったり、関連するプーリーのベアリングが焼き付いたりすると、ゴムが焼けるようなにおいが発生します。
- 触媒の異常過熱:前述の通り、失火によって未燃焼ガスが流れ込み、触媒が異常な高温になっている場合も、焦げ臭いにおいがすることがあります。
特に「オイルが焼けるにおい」や「ビニールが溶けるようなにおい」を感じた場合は、一刻を争う事態かもしれません。
車から離れて安全を確保した上で、消防への連絡も視野に入れつつ、JAFやロードサービスに救助を要請してください。
エンジン警告灯が点滅しガタガタ揺れた時の対処法
- 点滅後に警告灯が消えた場合はどうする?
- エンジンがガタガタする時の修理費用
- ホンダやダイハツの点滅時の注意点
- エンジン警告灯の点滅とガタガタは専門家へ
点滅後に警告灯が消えた場合はどうする?
エンジン警告灯が点滅し、一度エンジンを切り、再始動したら警告灯が消えて、ガタガタという振動も収まった、というケースがあります。
このような場合、「直ったのかもしれない」と安心してしまうかもしれませんが、それは危険な判断です。
結論として、一度でも点滅した場合は、たとえ症状が消えても必ず整備工場で点検を受けるようにしてください。
その理由は、車のECUにあります。ECUは、警告灯を点滅させた原因となったエラーの履歴を「故障診断コード(DTC)」として記憶しています。
症状が一時的に収まったとしても、根本的な原因(例えば、劣化しかけたイグニッションコイルや汚れが溜まったインジェクターなど)が解消されたわけではありません。
そのまま乗り続ければ、いずれ同じ症状が再発する可能性が非常に高いです。
プロの整備士は、専用の診断機(スキャンツール)を車に接続することで、ECUに記録された故障診断コードを読み取ることができます。これにより、現在症状が出ていなくても、「どのシリンダーで、いつ、どのような異常が起きたか」を正確に特定できるのです。
「様子を見る」という選択は、何の解決にもなりません。
むしろ、次に症状が出たときには、高速道路の走行中など、もっと危険な状況かもしれません。警告灯が消えたからといって安心せず、トラブルの根本原因を突き止めて修理するために、速やかに専門家へ相談しましょう。
関連記事
エンジンがガタガタする時の修理費用

エンジン警告灯の点滅と振動を伴う修理には、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。
費用は、原因となっている部品や車種、依頼する整備工場によって大きく変動しますが、以下に一般的な原因と費用の目安をまとめました。
注意:以下の費用はあくまで目安です。正確な金額は、必ず整備工場での診断後に提示される見積もりでご確認ください。また、下記の部品代・工賃に加えて、診断料として3,000円~8,000円程度が別途必要になることが一般的です。
| 原因箇所 | 主な修理内容 | 費用相場(部品代+工賃) | 備考 |
|---|---|---|---|
| スパークプラグ | 全数交換 | 8,000円 ~ 40,000円 | 消耗品。1本だけでなく、全気筒分を同時に交換するのが基本です。高性能なイリジウムプラグなどは高価になります。 |
| イグニッションコイル | 故障した気筒分を交換 | 1本あたり 15,000円 ~ 30,000円 | こちらも消耗品です。1本故障すると、他のコイルも近いうちに寿命を迎える可能性があるため、全数交換を推奨されることもあります。 |
| O2センサー | センサー交換 | 20,000円 ~ 50,000円 | 排気ガス中の酸素濃度を測るセンサー。警告灯点灯の主要な原因の一つです。 |
| インジェクター | 洗浄または交換 | 洗浄:1本 5,000円~ 交換:1本 30,000円~ | 部品自体が高価なため、交換になると費用がかさみます。 |
| エアフローセンサー | センサー交換 | 20,000円 ~ 80,000円 | エンジンが吸い込む空気の量を測るセンサー。車種によって価格差が大きいです。 |
最も頻度の高いイグニッションコイルやスパークプラグの交換であれば、数万円程度で収まることが多いです。
しかし、複数の部品が同時に故障していたり、触媒の交換など二次的な被害が及んでいたりすると、修理費用は10万円を超えることも珍しくありません。早期発見・早期修理が、結果的に費用を抑えることにつながります。
ホンダやダイハツの点滅時の注意点

エンジン警告灯の点滅とガタガタという症状は、特定のメーカーに限らず、どの車にも起こりうるトラブルです。
ホンダ車であってもダイハツ車であっても、基本的な原因や対処法はこれまで述べてきた内容と変わりありません。
重要なのは、メーカーを問わず「速やかに安全な場所に停車し、専門家に診断を依頼する」という原則を守ることです。ただし、メーカーや車種によっては、特有の傾向やリコール情報が存在する場合があります。
メーカーごとの対応
- ディーラーへの相談:ホンダ車ならHonda Cars、ダイハツ車ならダイハツの販売店など、正規ディーラーに相談するのが最も確実です。ディーラーは自社製品に関する豊富な知識とデータ、専用の診断機器を持っており、原因の特定がスムーズに進む可能性が高いです。
- リコール・サービスキャンペーンの確認:過去に、特定の車種でイグニッションコイルの不具合などがリコールやサービスキャンペーン(無償修理)の対象となっているケースがあります。ご自身の車が対象になっていないか、各メーカーの公式サイトで車台番号を入力して確認してみることをお勧めします。 (参照:本田技研工業株式会社 リコール・改善対策・サービスキャンペーン)(参照:ダイハツ工業株式会社 リコール・改善対策情報)
特に走行距離が多い軽自動車(ダイハツのタントやムーヴなど)では、イグニッションコイルやプラグの消耗が比較的早く進む傾向があるという情報もあります。定期的なメンテナンスが、こうしたトラブルを未然に防ぐ鍵となります。
いずれにせよ、自己判断で「このメーカーはここが弱いから」と決めつけるのは危険です。まずはプロによる正確な診断を受け、適切な修理を行うことが大切です。
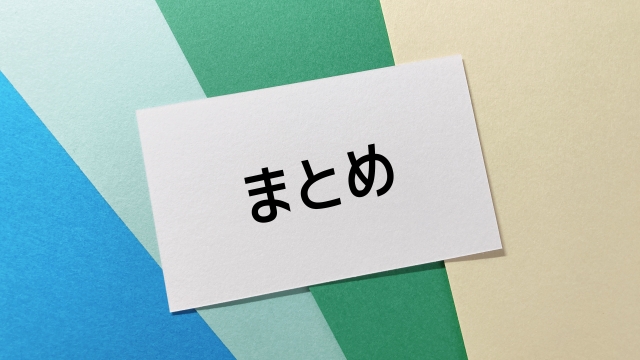
- エンジン警告灯の点滅とガタガタの主な原因はエンジンの失火
- 失火は点火系・燃料系・センサー系のトラブルから発生する
- 警告灯の「点滅」は「点灯」よりもはるかに危険なサイン
- 点滅は現在進行形で重大なトラブルが起きていることを示す
- オレンジ色の警告灯は「速やかな点検が必要」という意味
- チカチカする点滅は触媒の損傷など二次被害につながる警告
- スピードが出ない場合はECUがセーフモードに入っている可能性
- ガタガタと焦げ臭いにおいは火災の危険性があり即時停車が必要
- 点滅後に警告灯が消えてもECUにエラー履歴が残っている
- 症状が消えても放置せず必ず専門家の診断を受ける
- 修理費用は原因によって異なり数万円から数十万円になることも
- スパークプラグやイグニッションコイルの故障が比較的多い
- ホンダやダイハツなどメーカーを問わず基本の対処法は同じ
- ディーラーや信頼できる整備工場へ速やかに相談する
- レッカーサービスやロードサービスの利用も検討する
エンジン警告灯が点滅し車体がガタガタと振動する主な原因は、エンジンの「失火」です。
これは警告灯が単に「点灯」している状態よりもはるかに緊急性が高く、走行を続けると触媒コンバーターなど高価な部品に深刻なダメージを与える可能性があります。
特にスピードが出ない、焦げ臭いにおいがするといった症状は、極めて危険なサインです。
直ちに安全な場所に停車し、運転を中止してください。
たとえその後、警告灯が消えたとしても、故障の履歴は車に記録されているため、自己判断で乗り続けず、必ず速やかに整備工場で専門家による診断を受けることが重要です。
以上、この記事が参考になれば幸いです。
 smart-info
smart-info 


