ダイハツ車のエンジン警告灯が突然点灯すると、不安になる方も多いでしょう。
特に「エンジン警告灯がオレンジ色に光ったらどうすればいい?」「エンジン警告灯は自然に消えるの?」といった疑問が浮かぶかもしれません。
この記事では、ダイハツ車に特化したエンジン警告灯の消し方をわかりやすく解説します。
また、エンジン警告灯が点灯しても安全に走行できるのかや、主な原因についても詳しく触れています。
さらに、気になる修理代の目安も紹介しているため、警告灯の対処法や費用感が知りたい方にも役立つ情報が満載です。

車の安全を保ちながら、適切な対応方法を確認していきましょう。
- ダイハツのエンジン警告灯が点灯する原因や対処法を理解できる
- エンジン警告灯がオレンジ色に点灯した場合の対応方法がわかる
- エンジン警告灯を消す方法やリセットの手順が学べる
- エンジン警告灯が消えない場合の修理費用の目安を把握できる
【最初に結論】
この記事ではリセット方法を解説しますが、もし警告灯の原因がエンジンの故障だった場合、修理代は10万円〜50万円と超高額になるケースがあります。
無理に消して走行し、完全に壊れてからでは「ただの鉄屑」になってしまいます。
手遅れになる前に、「警告灯がついた状態でもいくらで売れるか」だけは確認しておいてください。
▶ 【公式】警告灯がついた車も高価買取!カーネクストの無料査定はこちら
ダイハツエンジン警告灯の消し方と基本知識

まず、ダイハツのエンジン警告灯が点灯したとき、焦らずに対処することが大切です。
エンジン警告灯は、エンジンやその周辺のシステムに異常がある場合に点灯し、ドライバーに注意を促します。
この警告灯はエンジン内部の問題を知らせてくれるもので、具体的にはエンジン制御システムの異常や電気系統のトラブル、センサーの不具合などが原因となります。

エンジン警告灯を消す方法としては、次の方法があります。
- バッテリー端子を外す方法:バッテリーの端子を外し、5~10分ほど待ってから再接続することで、ECU(エンジン制御ユニット)がリセットされ、警告灯が消える場合があります。
- ヒューズを外す方法:ヒューズボックス内の「EFI」または「ECU」のヒューズを一度外し、しばらく置いてから元に戻すことで消えることもあります。ただし、ヒューズを扱う際は正しい位置や操作を確認しながら行いましょう。
エンジン警告灯の役割は、車に不具合があることをいち早く知らせることです。
この警告灯が点灯した際、すぐに車を停止して原因を確認する必要があります。
エンジン内部やセンサーの不具合を無視して走行を続けると、エンジンが故障したり、さらなる問題が発生する可能性があるためです。
警告灯が点灯しているときは、まずエンジンや車両に異常がないか確認しましょう。
例えば、エンジンが異音を発している、振動が通常より激しい、異臭がする場合などは、エンジンや制御系統の異常が考えられます。
また、バッテリーの端子がしっかりと接続されているか、ガソリンキャップがきちんと閉まっているかといった基本的な点もチェックしましょう。
上記の方法で警告灯が消えない場合、問題が解決していないか、別の箇所に異常が残っている可能性があります。
この場合、車を整備工場やディーラーに持ち込むことをお勧めします。ディーラーでは、専用の診断機を使ってエラーコードを読み取り、問題の原因を詳細に把握することができます。
エンジン警告灯が点灯すると不安に感じるかもしれませんが、慌てずに原因を確認し、対処することが重要です。
バッテリー端子やヒューズを外すことで一時的に消える場合もありますが、根本的な問題が残っている可能性があるため、確実な診断を受けてから走行するようにしましょう。
エンジン警告灯が点灯する原因

ダイハツのエンジン警告灯が点灯する原因はいくつか考えられ、いずれも車の状態に注意を促す重要なサインです。ここでは、よくある原因を簡単に説明します。
現代の車には、エンジンの動作や空気の流れ、燃料の量を管理するために複数のセンサーが組み込まれています。
ダイハツ車の場合、O2センサーやエアフローセンサー、イグニッションセンサーといったセンサーが異常を検知すると、エンジン警告灯が点灯します。
たとえば、O2センサーの異常は、排気ガスに含まれる酸素量を正常に測れなくなり、燃費が悪化することにもつながります。
バッテリーの接続がゆるんでいたり、バッテリー自体が劣化していると、エンジン警告灯が点灯することがあります。
特に、バッテリー交換後などに接続がしっかりとできていない場合は要注意です。
劣化が進んでいるときも警告灯が点灯するため、定期的なチェックが必要です。
意外かもしれませんが、給油口のキャップがしっかり閉まっていないと、内部の圧力が調整できず警告灯が点灯することがあります。
給油後に警告灯が点灯した場合は、キャップが正しく閉まっているか確認してみましょう。
エンジン内で燃焼がうまくいかず、排気ガスの成分に異常が生じた場合も警告灯が点灯する原因となります。
排気システムに異常があると、車全体のパフォーマンスに影響が出るため、早めに確認することが大切です。
エンジンをかけるための点火を行うパーツであるイグニッションコイルやスパークプラグが故障していると、エンジン警告灯が点灯することがあります。
点火がうまくいかないとエンジンの動作が不安定になり、振動や加速不良の原因にもなるため、これらの部品が古くなっている場合は交換が推奨されます。
車には、エンジンの状態を監視し続けるコンピュータ(ECU)が搭載されていますが、このコンピュータが誤作動を起こしてエラーを検知した場合も警告灯が点灯することがあります。
エンジンに直接の問題がない場合もあるため、コンピュータエラーのリセットが必要になるケースもあります。
これらのように、エンジン警告灯が点灯する原因はさまざまです。
警告灯が点灯した際は、早めに原因を突き止め、必要に応じて整備工場でのチェックを受けることが車の安全性を保つために重要です。
エンジン警告灯がオレンジ色に光ったらどうすればいい?

エンジン警告灯がオレンジ色に点灯すると、エンジンや車のシステムに何らかの異常が発生していることを示しています。しかし、すぐに走行を停止する必要はありません。
ここでは、オレンジ色の警告灯が点いたときに取るべき対応を順を追って解説します。
オレンジ色の警告灯が点灯した場合、慌てずに、できるだけ早く安全な場所に車を停めましょう。エンジンや車のシステムの調子が悪い可能性があるため、高速道路や交通量の多い場所では、事故を防ぐためにも落ち着いて対処することが大切です。
車を停めたら、異常な音や匂いがしないか、振動が激しくないかなど、車の状態を確認してください。何も異常が見当たらない場合、軽度のエラーの可能性がありますが、異常が感じられる場合は、走行を控え、点検を優先するようにしましょう。
一時的なエラーが原因で点灯することもあるため、一度エンジンを切って数分待ってから再始動するのも一つの手段です。エンジンを再始動した際に警告灯が消えれば、一時的なエラーの可能性が高いですが、再度点灯する場合は問題が続いていることを示しているため、注意が必要です。
警告灯が消えない場合は、早めに整備工場で点検を受けることが重要です。異常を知らせるために警告灯が点灯しているため、放置すると症状が悪化し、修理費用が高額になる可能性もあります。また、定期点検を受けておくと、再発の予防にもつながります。
オレンジ色の警告灯が点いている間は、負荷がかかる急な加速や長距離運転は避けるのが賢明です。特に長時間の走行や高回転の使用はエンジンに負担がかかり、症状が悪化する原因にもなりかねません。車の状態が気になる場合は、無理せず点検を依頼しましょう。

オレンジ色の警告灯が点灯した場合は、焦らずに、車と周囲の安全を最優先に対応することが大切です。
エンジン警告灯は自然に消える?

エンジン警告灯が点灯したとき、自然に消えるかどうかは、エラーの原因と状況によって異なります。
ここでは、警告灯が自然に消える場合と、消えない場合の違いを説明します。
一時的なエラーでエンジン警告灯が点灯した場合、状況によっては自然に消えることがあります。
例えば、センサーが一時的に誤作動した場合や、気温や湿度の影響で一時的に警告が出ることもあります。
このようなケースでは、エンジンをかけ直すと警告灯が消える場合もあります。
エンジン警告灯が消えない場合は、何らかの異常が続いていることを示しているため、放置しないことが重要です。
この場合は、車を点検に出すことをおすすめします。エンジンやシステムの不具合が解消されないと警告灯は消えないため、修理が必要なケースも少なくありません。
仮に警告灯が自然に消えたとしても、一度でも点灯した場合は点検を受けたほうが安心です。
警告灯の点灯は何らかの異常を示していた可能性があり、車の状態をしっかり確認しておくと、今後の故障やトラブルを防げるからです。
頻繁にエンジン警告灯が点灯し、しばらくして消えるといったことが続く場合は、システムやセンサーに根本的な問題がある可能性があります。
この場合、走行に支障が出ることもあるため、早めに点検を依頼しましょう。
エンジン警告灯は一時的に自然に消えることもありますが、放置せず、車の安全と性能を保つためにも必要な対応を心がけましょう。

エンジン警告灯については、より詳しくこちらの記事で解説しています↓
エンジン警告灯が点灯しても走っても大丈夫?

エンジン警告灯が点灯すると、不安になる方も多いですが、必ずしもすぐに停止しなければならないわけではありません。
しかし、走行を続けることにはいくつかの注意点があります。ここでは、点灯したときに走行可能かどうかの判断基準について説明します。
エンジン警告灯がオレンジ色の場合は、走行は可能ですが注意が必要です。
オレンジ色の警告灯は「点検が必要」というサインであり、すぐに危険な状態ではないものの、できるだけ早めに点検や修理を検討するのが望ましいです。
赤色の警告灯が点灯している場合は、ただちに車を停め、安全な場所でエンジンを切りましょう。
赤色の点灯はエンジンや車の重要なシステムに重大な問題が発生していることを示しています。
このまま走行を続けると、車が故障したり、事故の原因になることがあります。
警告灯が点灯していて、加速が鈍くなったり異音がする場合は、無理に走行を続けないようにしてください。
異常がある状態での走行は、車の部品やエンジンにダメージを与える可能性があるため、速やかに整備工場へ連絡し、点検を依頼するのが安心です。
警告灯が点灯したままの状態を放置すると、車の性能が低下するだけでなく、修理費用が高くなる場合もあります。
エンジン警告灯が点灯した際は、念のため速やかに点検を受け、不具合を解消しておくことが、安全かつ経済的な選択です。
エンジン警告灯が点灯してもすぐに危険とは限りませんが、状況に応じて冷静に判断し、必要であれば点検を受けることが大切です。
ダイハツ エンジン警告灯 消し方と対処法
- ダイハツの警告灯の種類と役割一覧
- ダイハツ車のエンジン警告灯の修理代・費用目安
- エンジン警告灯のリセット方法(トヨタの場合)
- エンジン警告灯の消し方(スズキの場合)
- 警告灯が点灯した際の専門家への相談のタイミング
ダイハツの警告灯の種類と役割一覧

ダイハツ車には、さまざまな警告灯が装備されており、それぞれ異なる役割でドライバーに車の状態を知らせています。
ここでは代表的な警告灯とその役割を一覧で紹介します。警告灯の意味を理解することで、車の異常を早めにキャッチし、安全な走行が可能になります。
1. エンジン警告灯
エンジン警告灯は、車のエンジンに異常が発生したときに点灯します。
通常、オレンジ色で表示され、「エンジンの点検が必要」というサインです。
センサーの異常や燃料の問題、排気ガスの不具合など、さまざまな要因で点灯します。
点灯時には、できるだけ早めに点検を受けましょう。
2. バッテリー警告灯
バッテリー警告灯が点灯するのは、バッテリーの電力が不足している、または充電系統に問題があるときです。
この警告灯が点いた場合は、バッテリーやオルタネーターに不具合があるかもしれません。
早急な対応が求められる場合が多いです。
3. ブレーキ警告灯
ブレーキ警告灯は、パーキングブレーキの操作やブレーキ液の不足、ブレーキシステムの異常を知らせます。
赤色で点灯することが多く、非常に重要な警告灯の一つです。
ブレーキに問題がある場合、走行に大きなリスクが伴うため、速やかな点検が必要です。
4. ABS警告灯
ABS警告灯は、ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)に問題があるときに点灯します。
通常はオレンジ色で表示され、ABSが正常に機能しない可能性があることを意味します。
点灯していても通常のブレーキは使えますが、緊急時の安全性に影響するため、点検が推奨されます。
5. オイル警告灯
オイル警告灯が点灯するのは、エンジンオイルの量や圧力が不足しているサインです。
この警告灯が点灯した場合、エンジン内部の潤滑が不十分になる恐れがあり、エンジンの故障につながる可能性があります。
エンジンの保護のため、早急にオイルの点検や補充を行いましょう。
6. 水温警告灯
水温警告灯は、エンジン冷却水の温度が高すぎるときに点灯します。
赤色で点灯する場合は、すぐにエンジンを切り冷やす必要があるため、点灯時には直ちに停車しましょう。
冷却系統の異常や水漏れが原因の場合もあるため、点検が必要です。
7. シートベルト警告灯
シートベルト警告灯は、運転席や助手席のシートベルトが装着されていない場合に点灯します。
安全運転のために重要な警告灯ですので、シートベルトが確実に装着されているか確認してください。
これらの警告灯が点灯した際には、それぞれの役割に応じた対応をすることが重要です。
警告灯が点いたらすぐに対処することで、安全な走行を保ち、車の長寿命化にもつながります。

その他にも以下のような警告灯の表示があります。
タントの取扱説明書より引用



ダイハツ車のエンジン警告灯の修理代・費用目安

エンジン警告灯が点灯すると、修理代が気になるところです。
ダイハツ車のエンジン警告灯に関連する修理費用は、原因や必要な修理内容によって大きく異なりますが、ここでは一般的な費用目安を解説します。
エンジン警告灯が点灯した際、多くの場合、原因の特定には専門の診断機器を使用します。
ディーラーや整備工場での診断料は通常、3,000円〜5,000円程度が目安です。
この診断により、どこに問題があるかを確認し、その後の具体的な修理内容が決まります。
エンジン警告灯の原因でよくあるのがO2センサーの不具合です。
O2センサーは排気ガスの酸素量を測る重要な部品で、不調があると警告灯が点灯します。
この場合の交換費用は、部品代と工賃を合わせて約15,000円〜30,000円が目安となります。
部品の種類や車種によっても変わりますが、純正品を使用する場合は少し高額になることもあります。
エアフロセンサーもエンジン警告灯の点灯原因の一つです。
エアフロセンサーはエンジンに送られる空気の量を計測するセンサーで、これが故障すると燃費や加速に影響が出るため早めの対応が必要です。
交換費用は15,000円〜25,000円程度が一般的です。
エンジンの点火に関わるイグニッションコイルやスパークプラグも、警告灯が点灯する原因になることがあります。
イグニッションコイルの交換費用は1本あたり10,000円〜20,000円、スパークプラグは3,000円〜5,000円程度です。
エンジンの種類によっては複数交換が必要になる場合もあるため、費用は部品の数によって異なります。
ダイハツ車でエンジン警告灯が点灯した場合、診断費用や部品交換費用を合わせて10,000円から40,000円程度が一般的な目安です。
費用は故障の原因や部品の種類によって変動します。
異常を感じたら、早めにディーラーや整備工場での診断を受けることが重要です。
【FP(ファイナンシャルプランナー)ヒロシの「損得」判断】
もしあなたの車が「年式10年落ち」や「走行距離10万km」を超えているなら、高額な修理をするのは経済的に大赤字です。
一箇所直しても、すぐに別の場所が壊れる「修理スパイラル」に陥るからです。
賢い人は、警告灯がついたタイミングを「乗り換えのサイン」と捉えて、修理代を次の車の頭金に回しています。

まずは「修理代」と「買取額」を天秤にかけてみましょう。
エンジン警告灯のリセット方法(トヨタの場合)

トヨタのエンジン警告灯をリセットする方法は、いくつかの手順で対応可能です。
ただし、自己流でリセットを試す前に、まずは異常の原因が解消されているかを確認することが大切です。
警告灯はエンジンや安全性に関わる問題を知らせる重要なサインであるため、原因がわからないままリセットしても再点灯することが多いためです。
一つ目のリセット方法として、バッテリー端子を一度外す方法があります。
具体的には、次の手順を試してみてください。
- 車のエンジンを完全にオフにします。
- バッテリーのマイナス端子(黒いケーブル側)を外し、10分程度放置します。
- その後、再度バッテリー端子を接続し、エンジンをかけて警告灯が消えたか確認します。
この方法は比較的簡単にできるため、まず試してみるリセット方法です。
ただし、車によってはオーディオや時計の再設定が必要になることもありますので注意しましょう。
より確実にエラーコードを消去するには、OBD2(車両自己診断システム)診断機を使う方法が効果的です。
こちらは専用機器が必要ですが、次の手順で行えます。
- OBD2診断機を車のOBDポートに接続します(通常、運転席の足元にあります)。
- 診断機のリセット機能を使ってエンジン警告灯をオフにします。
- リセット後、エンジンをかけ直して警告灯が消えたか確認します。
OBD2診断機はカー用品店やインターネットで購入可能です。
エンジンの状態を把握できるため、今後のメンテナンスにも役立ちます。

整備工場に行かなくても、この診断機を挿すだけでスマホでエラーコード(原因)を確認できます。
ボッタクリ防止にもなるので1つ持っておくと便利
原因が特定できずにリセットした場合、警告灯が再び点灯することがあります。
このような場合は、専門の整備工場やディーラーで診断してもらうのが安心です。
警告灯が点灯していると車検に通らない可能性もあるため、確実に異常を解決したうえでリセットすることが重要です。
トヨタのエンジン警告灯のリセットは、これらの方法で対処できますが、原因をしっかりと突き止め、必要に応じて専門家の助けを借りるようにしましょう。
エンジン警告灯の消し方(スズキの場合)

スズキのエンジン警告灯を消す方法はいくつかありますが、まずは点灯の原因を把握することが大切です。
原因が特定されずに消してしまうと、再点灯してしまう可能性が高いため、注意して取り組むようにしましょう。
最も簡単に試せる方法は、バッテリー端子を一度外してエンジン警告灯をリセットすることです。手順は次の通りです。
- 車のエンジンを完全に切ります。
- バッテリーのマイナス端子(黒いケーブル側)を外し、10〜15分程度待機します。
- 再度バッテリー端子を取り付け、エンジンをかけて警告灯が消えたか確認します。
ただし、この方法は簡単ですが、オーディオや時計の設定がリセットされるため、再設定が必要になることがあります。
スズキ車の多くでは、エンジンルーム内にある「EFI」ヒューズを抜く方法でもリセットが可能です。手順は以下の通りです。
- エンジンルームのヒューズボックスを開け、EFIヒューズを探します。
- EFIヒューズを一度取り外し、1分程度待機します。
- 再度ヒューズを元に戻し、エンジンをかけて警告灯が消えているか確認します。
ヒューズを抜いて消す方法も簡便ですが、ヒューズの場所がわかりにくい場合もあるため、車の取扱説明書を参考にしましょう。
自分でリセットしても警告灯が消えない場合や、原因がわからないまま消そうとするのは避けたほうが無難です。
この場合、整備工場やディーラーで専用の診断機を使って原因を調べ、必要に応じてリセットしてもらうのが安心です。
エンジン警告灯が点灯している状態で無理に走行を続けると、車にダメージを与える可能性もあります。確実に原因を解決した上で、適切にリセットを行うよう心がけましょう。
警告灯が点灯した際の専門家への相談のタイミング

エンジン警告灯が点灯した場合、すぐに対応が必要か迷うことがあるかもしれません。ここでは、どのタイミングで専門家に相談すべきかについて説明します。
エンジン警告灯が赤色に点灯している場合は、直ちに車を安全な場所に停め、エンジンを切ることが必要です。
赤色は緊急性が高く、エンジンや車両の安全に関わる重大なトラブルを示しています。
この場合は、レッカーサービスを依頼し、整備工場やディーラーへ持ち込むことを優先しましょう。
警告灯がオレンジ色の場合は、緊急性はそれほど高くないものの、できるだけ早めに専門家に相談するのが安心です。
オレンジ色の警告灯は「要点検」のサインであり、エンジンやセンサーに軽度の異常が見られる可能性があります。
通常の走行に支障がなくても、後に不具合が悪化する可能性があるため、なるべく早く診断を受けることが重要です。
エンジン警告灯が点灯していない場合でも、異常音がしたり、加速が鈍く感じられる場合は、トラブルの兆候かもしれません。
このような状況が見られたら、点検のタイミングを待たずに早めに整備工場に相談することで、重大な故障を未然に防げる可能性が高まります。
一時的にエンジン警告灯が消えたとしても、念のため点検を受けるのが賢明です。
エンジン警告灯が一度でも点灯するということは、何らかの異常が発生していた可能性があるためです。
警告灯が消えたからといって完全に問題が解決したわけではないことが多いため、安全を考慮し専門家に相談することをおすすめします。
エンジン警告灯が点灯していなくても、車検前や長距離を走行する前には整備工場での点検を受けることが安心です。
特に車検の際、警告灯が点灯していると合格できない可能性があるため、早めの点検・整備で安全を確保しましょう。
警告灯が点灯した際は、その色や状況に応じて適切なタイミングで専門家へ相談することが大切です。
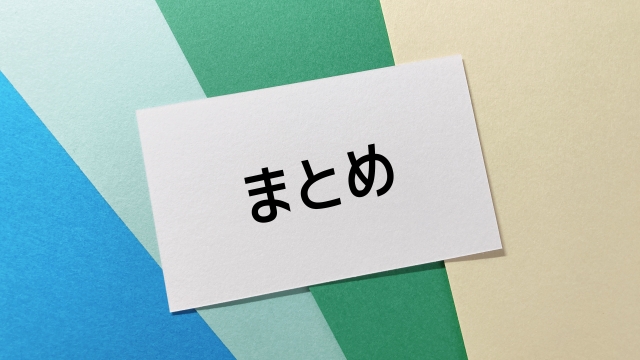
- エンジン警告灯はエンジンやその周辺システムの異常を知らせる
- ダイハツ車でエンジン警告灯が点灯した際は焦らずに対処する
- エンジン警告灯が点灯する主な原因はエンジン制御システムの異常や電気系統のトラブル
- 消し方には「バッテリー端子を外す」「ヒューズを抜く」方法がある
- バッテリー端子を外して5~10分待つとECUがリセットされる場合がある
- ヒューズボックス内のEFIまたはECUヒューズを外しリセットを試す方法もある
- 警告灯が点灯しているときはまずエンジンや車両の異常がないか確認する
- エンジン異音、異臭、振動などがある場合は無理な運転を控える
- 一時的なエラーでエンジン警告灯が自然に消える場合もある
- 異常が解消しない場合、警告灯は再度点灯するため注意が必要
- 点灯時の対処方法はエンジン再始動でエラーが解消するか確認すること
- 警告灯が消えない場合は整備工場やディーラーで点検を受けることが推奨される
- ダイハツのエンジン警告灯点灯原因にはバッテリー接続不良も含まれる
- バッテリー端子の接続不良や劣化により警告灯が点灯する場合がある
- 給油口キャップがゆるんでいるとエンジン警告灯が点灯することもある
- 排気システムの不調が原因で警告灯が点灯する場合がある
- イグニッションコイルやスパークプラグの不具合で警告灯が点灯する
- エンジン内部のセンサー異常で警告灯が点灯することが多い
- エンジン警告灯が点灯したら安全な場所に停車し車の状態を確認する
- 点灯が継続する場合、整備工場での早めの診断が推奨される
- エンジン警告灯が点灯したままでは車検に通らない場合がある
- 警告灯の点灯を無視するとエンジンや他の部品にダメージを与える可能性がある
- 長距離走行前や車検前にエンジン警告灯の点検を受けるのが安全
ダイハツ車のエンジン警告灯が点灯したら、まず焦らずに以下の方法を試しましょう。
バッテリー端子を一度外し、5〜10分待機後に再接続することでリセットを試みます。
次に、ヒューズボックス内の「EFI」や「ECU」ヒューズを抜き、数分待ってから戻す方法も有効です。
いずれの方法でも消えない場合は、根本的な問題が残っている可能性が高いため、整備工場やディーラーでの診断をおすすめします。
また、オレンジ色の警告灯ならすぐに停止する必要はありませんが、早めに点検を受けてください。
赤色の場合はただちに停車し、専門家に相談するのが安全です。
以上、この記事が参考になれば幸いです。
 smart-info
smart-info 


