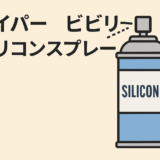この記事をご覧になっている方は、きっとタイヤ交換の際などに「ハブの防錆処理をしますか?」と提案された経験があるのではないでしょうか。
確かに、ハブに錆が付くとホイールの固着やナットの緩みといったトラブルにつながる可能性があります。
しかし、すべての車にとって「防錆塗装は必要か?」と考えると、その答えは使用環境やメンテナンス状況によって異なると言えます。
この記事では、「実際の効果はどのくらい?」といった疑問に答えながら、ハブ防錆の必要性を地域別・環境別に詳しく解説します。
また、「タイヤ交換のサビ取りは必要か」と迷う方に向けて、作業の重要性や注意点についても触れています。
さらに、ハブ防錆料金の相場や、ディーラーとイエローハット、エネオス、オートバックスなど業者ごとのサービス比較、自分でできる施工方法やおすすめの防錆スプレーも紹介します。
- ハブ防錆が必要かどうかの判断基準
- ハブに錆が付くことによるリスクと影響
- ハブ防錆の効果と施工方法の違い
- 各業者の料金やサービス内容の比較

無駄な出費を避け、車を長く快適に使うために、ぜひ最後までご覧ください。
ハブ防錆は必要かどうか徹底解説
- 防錆塗装は必要?
- ハブに錆が付くとどうなる?
- ハブ防錆の効果はどのくらい?
- タイヤ交換のサビ取りは必要?
- ハブ防錆は自分でできる?
防錆塗装は必要?

防錆塗装は、状況や使用環境によって必要性が大きく変わる作業です。
すべての車に絶対必要というわけではありませんが、一定の条件下では有効な対策となります。
まず、防錆塗装とは金属部分が酸化して錆びるのを防ぐためのコーティング処理を指します。
塗料やスプレーを使って金属の表面に膜を作り、水分や空気との接触を減らすことで、錆の発生を抑えることができます。
ここで重要なのは、どの程度の環境に車がさらされているかです。
例えば、雪が多く降る地域や海に近い沿岸部では、路面に散布される融雪剤(塩化カルシウム)や潮風により、金属部分が錆びやすい状態に常に置かれています。このような環境では、防錆塗装によってサビの進行を抑える効果が期待できます。
一方で、都市部や雨の少ない地域では、ハブや下回りにまで深刻なサビが発生するケースはそれほど多くありません。車両の使用頻度が少なく、常に屋根付きの駐車場に保管されているような場合は、無理に防錆塗装をする必要はないとも考えられます。
また、防錆塗装の施工方法にも注意が必要です。適切な下処理が行われないまま塗料を塗ると、逆に錆を閉じ込めてしまい、内部から腐食が進行する恐れもあります。特にハブのようにタイヤと密着する部分では、塗装によってホイールとの当たり面に不具合が生じるリスクもあるため、施工には一定の技術が求められます。
このように考えると、防錆塗装は「すべての車に必須」というものではなく、車の使用状況、保管環境、地域性などをふまえて判断すべきメンテナンスといえます。
ハブに錆が付くとどうなる?

ハブに錆が付くと、見た目の問題だけでなく、タイヤ交換時の作業や安全面に悪影響を及ぼす可能性があります。
ハブとは、タイヤと車両を接続する車輪の中心部分のことで、ホイールの裏側と密着する部位です。この部分が錆びると、ホイールとの密着性が損なわれ、走行中の微細な振動やズレの原因になることがあります。
具体的には、錆が進行することでホイールがハブに固着し、次回のタイヤ交換時に外れにくくなるケースがあります。これにより、通常の作業時間では取り外しが難しくなり、工賃が余計にかかってしまうこともあるでしょう。また、力づくで外そうとすると、ハブボルトなどの重要部品を損傷させるリスクも高まります。
さらに、錆によってホイールとの接地面が不均一になると、ナットの締め付けにムラが生じやすくなります。その結果、ナットが徐々に緩んでくる危険性もあり、最悪の場合、脱輪など重大なトラブルに発展するおそれも否定できません。
もちろん、すべての錆が即座に危険につながるわけではありません。
表面に薄く浮いた程度のサビであれば、ホイールを外した際にワイヤーブラシなどで軽くこすれば問題ない場合も多いです。しかし、長期間放置された重度のサビは、固着や締結不良といった実害を引き起こすことがあります。
このような理由から、ハブの錆を完全に放置することはおすすめできません。
定期的な点検と軽い錆落としだけでも、トラブルの予防には効果があります。特に年に2回、夏冬タイヤの履き替え時など、タイヤを外すタイミングで簡単なケアを行うと安心です。
ハブ防錆の効果はどのくらい?

ハブ防錆の効果は、使用する防錆剤や施工方法、車の使用環境によって変わりますが、おおよそ半年から1年程度が目安とされています。
ハブ防錆処理では、錆を落とした後に防錆剤を塗布することで、金属表面に保護膜を形成します。これにより、水分や空気の侵入を抑制し、酸化(錆)の進行を防ぐことができます。ただし、この防錆膜は永久的なものではなく、時間の経過や走行による摩擦、気候条件などによって徐々に効果が薄れていきます。
実際、多くのカー用品店や整備工場では、防錆処理の効果は「約1年間」と案内されています。これは防錆剤の持続性を基準にした目安であり、降雪地帯や潮風の強い地域ではもう少し短くなる可能性もあります。逆に、乾燥地帯や屋内駐車場に保管される車であれば、やや長持ちする場合もあるでしょう。
ただ、防錆処理をしたからといって、錆がまったく出ないわけではありません。特に、施工時に既に進行している錆があった場合や、塗布が不均一だった場合には、部分的に再発する可能性があります。そのため、防錆処理は「予防的メンテナンス」として位置づけるべきです。
さらに注意したいのは、防錆効果を長持ちさせるには適切な下処理が不可欠であるという点です。単にスプレーを吹きかけるだけでは、効果は短期間で終わってしまうことがあります。錆をしっかり落とし、脱脂をしてから施工することで、初めて本来の効果が得られるのです。
このように、ハブ防錆の効果は永続的ではないものの、タイヤ交換時に定期的に実施することで、ホイールの固着防止やメンテナンス性の向上につながります。年1回のペースで点検・再施工を行えば、安全性を維持しやすくなるでしょう。
タイヤ交換のサビ取りは必要?

タイヤ交換時のサビ取りは、車の安全性や作業性を保つうえで有効な処置ですが、必ずしもすべての車両に必要というわけではありません。状況に応じて適切に判断することが大切です。
まず、タイヤ交換の際にチェックすべきなのは「ハブ」と呼ばれるホイールと接触する部分の金属面です。
ここは雨水や融雪剤、湿気などの影響を受けやすく、錆が発生しやすい箇所のひとつです。軽度の錆であれば走行に大きな影響はないこともありますが、蓄積すればホイールの固着、ナットの締め付け不足、ハンドルのブレなどを引き起こす可能性もあります。
実際、ホイールとハブの接地面に厚く錆がこびりついていると、次のタイヤ交換時にホイールが取り外しにくくなるだけでなく、金属同士が固着することで工具を使っても外せない状態になることがあります。また、錆が表面だけでなく内部にまで進行すると、部品自体の強度にも悪影響を与える可能性があるため、早めの対応が望まれます。
とはいえ、タイヤ交換のたびに必ずサビ取りをしなければならないわけではありません。
たとえば、新車でまだ錆の兆候がない場合や、乾燥した地域で使用している車で錆のリスクが低い場合には、特別な処置は不要と考えられます。その際は、目視点検と簡単な清掃だけでも十分でしょう。
一方、降雪地帯に住んでいる方や、沿岸部のように潮風が強いエリアで車を使用している場合には、定期的なサビ取りを含めたメンテナンスが推奨されます。このような環境では錆の進行が早く、予防的な処置を怠るとトラブルにつながりかねません。
このように、タイヤ交換時のサビ取りは「必要な場合に行う」判断が重要です。交換作業を行う際には、ハブの状態をよく確認し、必要であればワイヤーブラシなどで錆を落とし、簡易的な防錆処理を施しておくことで、次回以降の作業効率と安全性を高めることができます。
ハブ防錆は自分でできる?

ハブ防錆は、ある程度の知識と道具があれば自分で行うことも可能です。ただし、適切な手順を守らないと逆効果になることもあるため、作業には十分な注意が必要です。
まず用意するものは、ワイヤーブラシ、パーツクリーナー、防錆剤(スプレータイプや錆転換剤など)、マスキングテープ、布またはペーパーウエスです。これらはホームセンターやカー用品店で手軽に購入できます。防錆剤は「金属用」「高温部対応」と記載されているものを選ぶと安心です。
作業の手順は、以下のようになります。
ハブ防錆の作業工程
| 手順 | 作業内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1 | タイヤを外す | 安全に車両をジャッキアップ |
| 2 | ハブを目視確認 | 錆の有無をチェック |
| 3 | 錆を除去 | ワイヤーブラシやサンドペーパー使用 |
| 4 | 汚れ・油分の除去 | パーツクリーナーを使用 |
| 5 | 表面を乾燥 | 濡れたままではNG |
| 6 | マスキング | ハブボルトや接地面を保護 |
| 7 | 防錆剤を塗布 | 均一にスプレーする |
| 8 | 乾燥時間の確保 | 製品によっては数時間必要 |
| 9 | タイヤを装着 | 最後にしっかり締め直す |
最初にタイヤを外し、ハブ部分を目視で確認します。もし錆が出ていれば、ワイヤーブラシやサンドペーパーでしっかりと削り落とします。
この工程を怠ると、防錆剤を塗っても効果が持続しにくくなります。その後、パーツクリーナーで油分や汚れを取り除き、乾燥させます。
次に、ホイール接地面に防錆剤をスプレーしますが、このとき注意したいのが「塗ってはいけない場所」です。
ハブボルトやホイールと直接接触する面に塗布してしまうと、グリップ力が落ち、走行中にホイールがずれたり、ナットが緩んだりするリスクが出てきます。そのため、塗布前にマスキングテープで養生しておくと安心です。
防錆剤を塗布した後は、しっかりと乾燥させる時間を設けましょう。
乾燥が不十分だと、防錆効果が低下するだけでなく、ホイール取り付け時にムラが生じてしまうこともあります。製品によっては乾燥時間が数時間かかる場合もあるので、説明書をよく確認してください。
また、自分で施工する場合は定期的な点検も欠かせません。
自動で効果を維持してくれるものではないため、半年~1年に1度は状態を確認し、必要に応じて再施工することが望ましいです。
このように、ハブ防錆はDIYでも十分対応可能ですが、作業手順を守らないと逆効果になるリスクもあるため、正しい知識を持って行うことが大切です。
初めての方は、最初はプロの施工を見たり、信頼できる動画やマニュアルを参考にするとよいでしょう。
ハブ防錆は必要か?業者ごとに比較
- ハブ防錆:料金の相場を解説
- ディーラーの料金とサービス内容
- イエローハットでのハブ防錆
- エネオスでハブ防錆をするメリット
- オートバックスの施工内容と価格
- おすすめのスプレーを紹介
ハブ防錆:料金の相場を解説

車両のハブ部分は、ホイールと直接接触する重要な箇所であり、サビが発生するとホイールの着脱が困難になるだけでなく、安全性にも影響を及ぼします。
そこで、ハブの防錆処理が推奨されていますが、その料金相場についてご説明いたします。
一般的に、ハブ防錆の料金は施工を行う店舗や車種、地域によって異なります。
例えば、大手カー用品店のイエローハットでは、ハブ防錆の作業工賃が税込3,960円からとなっており、作業時間は30分程度とされています。ただし、車種や店舗によって料金や作業時間が異なる場合がありますので、事前に各店舗へお問い合わせいただくことをおすすめします。
一方、ディーラーや他のカー用品店、整備工場などでもハブ防錆のサービスを提供している場合がありますが、料金は店舗ごとに設定されており、明確な相場は存在しません。そのため、複数の店舗に問い合わせて料金やサービス内容を比較検討することが重要です。
また、ハブ防錆は定期的なメンテナンスが推奨されており、サビの進行を防ぐことで将来的な修理費用を抑える効果も期待できます。料金だけでなく、施工の質やアフターサービスも考慮して、信頼できる店舗を選ぶことが大切です。
ディーラーの料金とサービス内容

自動車ディーラーでは、新車販売だけでなく、各種メンテナンスサービスも提供しています。ハブ防錆に関しても、多くのディーラーで対応が可能です。ディーラーでのハブ防錆の料金やサービス内容についてご紹介いたします。
ディーラーでのハブ防錆の料金は、メーカーや車種、さらにはディーラーの方針によって異なります。
具体的な料金は公表されていない場合が多いため、直接ディーラーにお問い合わせいただくことが必要です。一般的には、ディーラーでの作業は純正部品や指定の防錆剤を使用するため、カー用品店などに比べて料金が高めに設定されていることがあります。
サービス内容としては、ハブ部分のサビを丁寧に除去し、メーカー指定の防錆剤を塗布することで、サビの再発を防ぐ処置が行われます。また、ディーラーならではのメリットとして、車両全体の点検や他の部品の状態確認も同時に行ってもらえる場合があります。これにより、車両全体の安全性を高めることが可能です。
ディーラーでのハブ防錆を検討される際は、料金だけでなく、使用する防錆剤の種類や保証内容、他のメンテナンスサービスとの組み合わせなど、総合的に判断することが重要です。信頼できるディーラーと相談しながら、最適なメンテナンスプランを選択されることをおすすめします。
イエローハットでのハブ防錆
イエローハットは、全国展開している大手カー用品店であり、タイヤやオイル交換などのピットサービスを提供しています。ハブ防錆サービスもその一環として行われており、多くのドライバーに利用されています。
イエローハットでのハブ防錆サービスは、ホイールとハブ部分の固着原因となるサビを除去し、強力な浸透防錆剤を使用してハブ面のサビつきを防止するものです。これにより、ホイールの着脱がスムーズになり、安全性の向上が期待できます。定期的なメンテナンスとして、このサービスを利用することが推奨されています。
料金は税込3,960円からで、作業時間は30分程度とされています。
ただし、車種や店舗によって料金や作業時間が異なる場合がありますので、詳細については各店舗にお問い合わせいただくことが必要です。
イエローハットでは、WEB予約システムも導入されており、事前に予約を行うことで待ち時間を短縮し、スムーズな作業が可能となります。また、タイヤ交換やオイル交換など、他のメンテナンスサービスと併せて予約することもできるため、効率的な車両管理が実現できます。
ハブ防錆は、車両の安全性を維持する上で重要なメンテナンス項目の一つです。イエローハットのサービスを活用して、定期的な点検と防錆処理を行うことをおすすめします。
参考記事
https://www.yellowhat.jp/store_service/pitservice/pitmenu/tire.html
エネオスでハブ防錆をするメリット

エネオスは全国に展開する大手ガソリンスタンドチェーンであり、給油だけでなく車の整備・メンテナンスも手がけています。その中でも、タイヤ交換や車検のタイミングで案内されることの多いのが「ハブ防錆」です。エネオスでハブ防錆を行うことには、いくつかの実用的なメリットがあります。
まず最初のメリットは、タイヤ脱着のタイミングで気軽に依頼できる点です。
エネオスではタイヤ交換サービスも提供しており、作業中にハブの状態をチェックし、その場で防錆処理の必要性を判断してもらえることが多くあります。これにより、事前に別の整備工場を予約する手間がなく、効率よくメンテナンスを進めることができます。
また、ハブが錆びるとタイヤとホイールが固着し、交換時の作業が難航することがあります。エネオスの防錆サービスでは、専用の錆取り機材を使って表面の錆を落とし、防錆剤を塗布して再発を予防します。これにより、次回以降のタイヤ交換もスムーズに進めることができるでしょう。
もう一つのポイントは、店舗によっては防錆作業の価格が比較的手頃であることです。地域や店舗によって異なりますが、2,000円〜3,000円台で施工しているところが多く、ちょっとした追加メンテナンスとして気軽に利用できます。ただし、詳細な施工内容や使用する防錆剤の種類は各店舗により異なるため、事前の確認は必須です。
なお、エネオスの店舗スタッフは車の整備に精通しているとは限らないため、ハブに関する深い技術的な説明がされない場合もあります。その場合は、「どのような薬剤を使用するのか」「ホイールとの接触面には塗らないか」など、疑問点を自分から確認しておくことがトラブル回避につながります。
こうした特徴をふまえると、エネオスでのハブ防錆は、便利さ・スピード・コストのバランスが良く、日常的なメンテナンスとして利用価値のあるサービスといえます。
オートバックスの施工内容と価格
オートバックスはカー用品の販売と同時に、車のメンテナンスサービスにも力を入れている全国チェーンです。その中でも「ハブクリアコーティング」という名称で提供されているハブ防錆サービスは、多くのドライバーから支持されています。
この施工は、まずホイールを取り外し、ハブ部分に付着したサビをしっかりと除去するところから始まります。専用のワイヤーブラシや研磨工具を使って錆を物理的に取り除いたあと、防錆剤を均等に塗布します。この作業により、金属表面を酸素や水分から保護し、今後のサビの発生を抑制します。なお、ナットの取付け部分やボルトには防錆剤が付着しないように養生を施しているため、安全面にも配慮された施工内容となっています。
価格は1台分(前後4カ所)で税込2,200円~が一般的な相場です。
施工時間はおよそ15〜20分程度で、タイヤ交換やローテーションと合わせて依頼することが多いです。また、オートバックスでは事前にWEB予約が可能なので、混雑する時期でもスムーズに作業を受けられる点も利便性の一つです。
ただし、車両の大きさや状態によって作業時間や料金が変動することがあります。また、タイヤを脱着しない場合は別途で脱着料金がかかることもあるため、実際の費用は店舗で確認するのが確実です。
さらに、オートバックスの防錆作業には、約1年間の防錆効果が期待されています。定期的に施工を続けることで、ハブの状態を長期間良好に保つことができ、タイヤ交換時の固着や振動トラブルのリスクも軽減されます。
全体として、オートバックスのハブ防錆サービスはコストパフォーマンスが高く、安心して利用できる内容となっています。車検やタイヤ交換時にあわせて検討する価値のあるメニューです。
おすすめのスプレーを紹介
ハブ防錆を自分で行いたいという方にとって、防錆剤選びは非常に重要なポイントです。
数多くの製品が市販されていますが、使用目的に適したスプレーを選ぶことで、錆の進行を効果的に抑えることができます。ここでは、DIYユーザーに向けておすすめのハブ防錆スプレーをいくつか紹介します。
まず最初に紹介したいのが、呉工業の「長期防錆スプレー」です。
この製品は50~70ミクロンの半硬質な保護膜を形成し、長期間にわたり防錆効果を発揮します。高湿度環境や腐食性の高い状況下でも安定した性能を発揮するため、降雪地域や沿岸部など、サビのリスクが高い環境に特に適しています。乾燥時間は比較的短く、作業の効率も良好です。
次におすすめするのが、「赤サビ転換防錆剤(SOFT99)」です。
このスプレーは、すでに発生してしまった赤サビを黒色の防錆皮膜へと変化させる特徴があります。サビを削り落とすのではなく、化学的にサビの進行を止めることができるため、軽度〜中程度の錆に対して有効です。専用筆が付属しており、狙った場所に的確に塗布できるのもポイントです。
また、イチネンケミカルズの「ホイール固着防止剤」も注目の製品です。
これは防錆効果に加えて、タイヤとハブの密着部分が固着するのを防ぐ機能も兼ね備えています。スプレータイプで塗布が簡単なうえ、塗布箇所が視認しやすいグリーン色となっているため、作業のしやすさにも優れています。
これらのスプレーはいずれも1,000円前後から購入可能で、市販のカー用品店やインターネット通販で入手することができます。
ただし、使用前には必ず「高温部対応かどうか」「ホイール接地面に使えるか」などの使用条件を確認してください。
防錆スプレーは適切に使用すれば非常に効果的な製品ですが、塗布の際にホイールの接地面やボルト部分に付着させてしまうと、トルク不足や滑りの原因になることもあります。養生をしっかり行い、説明書をよく読んで正しく使用することが大切です。
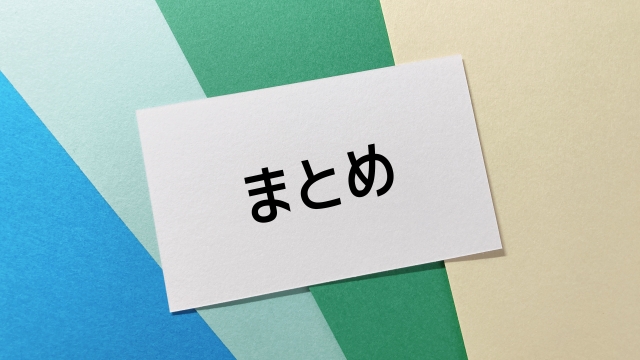
- 防錆塗装は地域や使用環境によって必要性が異なる
- 雪国や沿岸部では防錆処理が特に効果的
- 都市部や屋内保管の車両では不要な場合もある
- ハブに錆があるとホイールの固着や脱輪のリスクがある
- 軽度の錆はブラシで除去すれば問題ないケースもある
- ハブ防錆の効果は半年〜1年が目安
- 施工前の下処理が不十分だと効果が持続しにくい
- タイヤ交換時のサビ取りは作業効率と安全性向上に寄与する
- 降雪地帯や潮風の強い地域ではサビ取りの頻度を増やすべき
- ハブ防錆はDIYでも可能だが養生や乾燥時間に注意が必要
- 間違った場所への塗布は緩みや事故の原因になりうる
- イエローハットでは約3,960円で30分程度の施工が可能
- ディーラーは純正防錆剤使用で価格はやや高めに設定される
- エネオスは利便性と手軽さがメリットだが施工内容は要確認
- オートバックスは2,200円〜で施工内容とコスパが良好
ハブ防錆は必ずしも全車に必要ではありませんが、雪道や沿岸部などサビが発生しやすい環境では効果的です。
ホイールの固着や脱輪を防ぐためにも、特に年2回のタイヤ交換時に点検・処理をするのがおすすめです。
都市部や屋内保管なら不要な場合もありますが、使用環境に応じて判断しましょう。
以上、この記事が参考になれば幸いです。
関連記事
 smart-info
smart-info