この記事では以下のような悩みにお答えします。
- オートマ車やMT車の発進手順が覚えられず、混乱してしまう
- 安全確認のやり方やタイミングがわからず、不安を感じる
- スムーズに発進できず、エンストや急発進をしてしまう
発進手順を正しく覚えずに運転すると、焦って誤操作をしてしまい、後続車に迷惑をかけたり、交通事故を引き起こす危険性があります。
特に、発進時の安全確認を怠ると、歩行者や自転車との接触事故のリスクが高まります。
また、発進時にスムーズに動き出せないことで、運転への自信を失い、ストレスを感じることにもつながります。
そこで、この記事では「車の発進手順と覚え方」をわかりやすく解説し、オートマ車とMT車の違い、安全確認の流れ、スムーズに発進するコツを紹介します。
また、発進を確実に覚えるための練習方法や注意点についても詳しく説明しています。
この記事でわかること
- 正しい発進手順を身につけ、迷わず操作できるようになる
- 発進前の安全確認のポイントを理解し、事故のリスクを減らせる
- スムーズな発進ができるようになり、運転の不安が解消される
- 効果的な練習方法を知り、短期間で発進の流れを身につけられる
車の発進手順を正しく覚えることで、安全かつスムーズに運転できるようになります。
特に初心者の方は、基本的な手順と安全確認をしっかりマスターすることが重要です。
この記事を参考に、確実な発進方法を身につけ、安心して運転できるようになりましょう。
- オートマ車とMT車の発進手順の違いと覚え方
- 発進前の安全確認の重要性と正しい手順
- サイドブレーキやシフトレバーの適切な操作方法
- スムーズな発進を身につけるための具体的な練習方法
車の発進手順と覚え方のポイント
- オートマ車の発進手順を覚えるコツ
- MT車の発進手順と覚え方の違い
- 発進前の安全確認の重要性と手順
- サイドブレーキの役割と発進時の操作
- ハンドブレーキとドライブ、どっちが先?
オートマ車の発進手順を覚えるコツ

オートマ車の発進手順は、マニュアル車に比べるとシンプルですが、初めて運転する人にとっては戸惑うこともあります。
特に、順番がごちゃごちゃになってしまったり、教習所で指導員ごとに言われることが違ったりすると、混乱しやすいでしょう。
ここでは、発進手順をスムーズに覚えるためのコツを紹介します。
まず、発進手順を「意味と目的」とセットで覚えることが大切です。
ただ単に「こうすればいい」と暗記するのではなく、「なぜこの動作が必要なのか」を考えることで、自然と身につきやすくなります。
例えば、最初にブレーキを踏みながらエンジンをかける理由は、誤って車が動き出すのを防ぐためです。
このように、一つひとつの動作の目的を理解すると、手順が頭に入りやすくなります。
次に、「3つのステップ」に分けて考えると整理しやすくなります。
- 第一ステップは「発進準備」
- 第二ステップは「安全確認」
- 第三ステップは「発進操作」
具体的には、第一ステップでシートやミラーの調整、シートベルトの装着、エンジン始動を行います。
第二ステップでは、ルームミラー・サイドミラー・目視での安全確認を行い、方向指示器を出します。
最後の第三ステップで、ブレーキペダルを徐々に離し、アクセルを踏んで発進します。
このように段階的に覚えることで、流れを意識しながらスムーズに操作できるようになります。
また、手順を「声に出して確認しながら運転する」方法も効果的です。
例えば、「ブレーキを踏む、エンジンをかける、シフトレバーをDに入れる……」といった具合に、手順を口に出しながら行うことで、体と頭で記憶しやすくなります。
特に、初心者のうちは焦ってしまうことが多いので、落ち着いて確認しながら進めることが大切です。
さらに、実際に運転する前に「イメージトレーニング」を行うのも有効です。
座学の時間や自宅で、頭の中で発進の手順をシミュレーションしてみましょう。
手を動かしながら、シフトレバーを操作する動作を再現すると、より実践的に覚えられます。
このように、オートマ車の発進手順を覚えるためには、「動作の意味を理解する」「ステップに分けて考える」「声に出して確認する」「イメージトレーニングを活用する」ことがポイントになります。
焦らず、繰り返し練習することで、自然と手順が身につくようになるでしょう。
MT車の発進手順と覚え方の違い

MT車(マニュアル車)は、オートマ車とは異なり、発進時にクラッチ操作が必要になります。
そのため、発進手順が少し複雑になり、初心者にとっては習得が難しいと感じることが多いでしょう。
ここでは、MT車の発進手順と、オートマ車との違いを整理しながら、覚え方のポイントを解説します。

MT車の発進手順は、大きく分けて「準備」「クラッチ操作」「アクセル調整」の3つのステップに分かれます。
まず、運転席に座ったら、シートとミラーを調整し、シートベルトを締めるのはオートマ車と同じです。
その後、エンジンをかける前にギアがニュートラルになっていることを確認し、クラッチペダルを踏みながらエンジンを始動させます。
次に、クラッチ操作を行います。
ギアを1速(ロー)に入れた状態で、クラッチを徐々に上げながら、同時にアクセルを少しずつ踏みます。
このとき、クラッチを急に離してしまうとエンストしてしまうため、半クラッチを意識しながら、ゆっくりと調整することが重要です。
半クラッチの感覚を掴むまでは、何度か練習する必要があります。
一方で、オートマ車はクラッチ操作が不要で、シフトレバーをDに入れれば発進できるため、操作の手間が大幅に減ります。
しかし、MT車の場合はクラッチを適切に調整しながらアクセルを踏むことで、スムーズに発進する必要があります。
そのため、最初のうちは「エンストするのではないか」という不安が生まれやすいですが、クラッチをゆっくり上げることを意識すれば、徐々に慣れていくでしょう。
覚え方としては、「左足のクラッチ操作と右足のアクセル操作を連携させる」ことを意識するとよいです。
また、動作を分解して考えると理解しやすくなります。
例えば、「まずクラッチを踏む→ギアをローに入れる→アクセルを軽く踏みながらクラッチをゆっくり上げる」といった形で、一つずつの動作を順番に整理すると、混乱せずに覚えられます。
このように、MT車はクラッチ操作が必要であり、オートマ車とは発進手順が異なります。
しかし、基本的な安全確認の手順は共通しているため、しっかりと基礎を身につけることが大切です。
繰り返し練習を行い、半クラッチの感覚を掴むことで、スムーズな発進ができるようになるでしょう。

半クラッチ上達のコツをこちらの記事で詳しく解説しています。よろしければ参考にしてみてください。
発進前の安全確認の重要性と手順

車を発進させる際、最も重要なのが「安全確認」です。
安全確認を怠ると、歩行者や自転車との接触事故、後続車との衝突など、重大な事故を引き起こす原因になります。
そのため、発進前には必ず周囲の状況を確認し、事故を未然に防ぐ意識を持つことが大切です。
安全確認の手順としては、まず「ルームミラーで後方の確認」を行います。
これは、自分の車の真後ろにいる車両や歩行者の位置を把握するために重要です。
次に、「左サイドミラーを確認」し、歩行者や自転車の有無をチェックします。
特に、路肩に寄せて停車している場合、車の左側を自転車が通る可能性があるため、十分に注意しましょう。
その後、「右サイドミラーを確認」し、後続車や並走している車がいないかをチェックします。
さらに、ミラーでは死角になる部分があるため、必ず「目視での確認」も行います。
例えば、左後方と右後方を直接振り返って確認することで、ミラーでは見えない部分の安全を確保できます。
最後に、「方向指示器(ウインカー)を出す」ことで、発進の意思を周囲に知らせます。
ウインカーを出した後、3秒間は進路変更せずに安全確認を続けることで、他の車に対して発進の準備をしていることを伝えられます。
安全確認を徹底することで、発進時の事故リスクを大幅に減らすことができます。
焦らず、確認の手順を確実に実施し、常に周囲への注意を怠らないことが、安全運転の基本となるでしょう。
サイドブレーキの役割と発進時の操作

サイドブレーキ(パーキングブレーキ)は、車を駐停車時に固定し、勝手に動き出さないようにするための重要な装置です。
オートマ車・マニュアル車に関係なく、安全な運転のために必ず正しく使用する必要があります。
特に、発進時の操作では、適切な順番で解除しなければ、車に負担をかけたり、スムーズな発進ができなかったりすることがあります。
サイドブレーキの主な役割は、「駐車時の車両固定」と「坂道発進時の補助」の2つです。
まず、駐車時には、シフトレバーを「P(パーキング)」に入れるだけでなく、サイドブレーキをかけることで、より確実に車を固定できます。
シフトレバーだけでは、車の重量や地面の傾斜によってわずかに動いてしまうことがあるため、サイドブレーキを使用することが推奨されています。
また、坂道発進時には、サイドブレーキを利用することで、後ろに下がるのを防ぎながらスムーズに発進できます。
特にマニュアル車では、クラッチ操作とアクセル操作の間に車が後退してしまうことがありますが、サイドブレーキをかけた状態で発進準備をすることで、安全に車を動かすことができます。
オートマ車の場合も、勾配が急な坂道では、サイドブレーキを活用すると安定した発進が可能です。
発進時の操作については、基本的に「ブレーキを踏みながらサイドブレーキを解除し、アクセルを踏む」という流れになります。
サイドブレーキを解除する前に、まずは通常のブレーキペダルを踏んでおくことが重要です。
これにより、サイドブレーキを解除した瞬間に車が動き出すのを防ぐことができます。
特に、坂道発進では、ブレーキペダルをしっかり踏みながら、アクセルを軽く踏んで車に前進する力を加えた状態で、サイドブレーキを解除するとスムーズに発進できます。
発進時にサイドブレーキを解除し忘れると、ブレーキがかかったまま走行することになり、燃費が悪化したり、ブレーキが過熱して故障の原因になる可能性があります。
発進時の違和感(重さや異音)を感じたら、サイドブレーキが解除されているかを必ず確認しましょう。
このように、サイドブレーキは安全運転をサポートする重要な装置です。
発進時には適切な順番で解除し、特に坂道発進時には慎重に操作することで、安全かつスムーズな運転を心がけることが大切です。
関連記事
ハンドブレーキとドライブ、どっちが先?

オートマ車の発進時、「シフトレバーをD(ドライブ)に入れてからハンドブレーキを解除するのか、それともハンドブレーキを先に解除するのか」という疑問を持つ人は多いでしょう。
結論としては、「ハンドブレーキを解除するのは、シフトレバーをDに入れた後」が正しい順番です。
発進時の手順を考えると、最初にブレーキペダルを踏みながらエンジンをかけ、シフトレバーをDに入れる流れになります。
ここで、ハンドブレーキを解除してしまうと、勾配がある場所では車が動き出す可能性があります。
これを防ぐために、シフトレバーをDに入れてから、ハンドブレーキを解除するのが安全な方法です。
ハンドブレーキ(パーキングブレーキ)は、車を完全に停止させるための装置ですが、シフトレバーがP(パーキング)に入っていない状態で解除すると、ブレーキペダルを踏んでいない限り車が勝手に動き出してしまうことがあります。
特に、傾斜のある場所では、わずかな傾斜でも車が動くリスクが高いため、必ずシフトレバーをDにした後に解除することを意識しましょう。
坂道発進の際には、ブレーキペダルをしっかり踏んだ状態で、シフトレバーをDに入れ、その後アクセルを少し踏みながらハンドブレーキを解除する方法が適切です。
この手順を守ることで、車が後ろに下がるのを防ぎながら、安全に発進できます。
なお、停車時の手順についても、正しい順番で行うことが重要です。
停車する際は、まずブレーキペダルを踏んで車を完全に停止させ、その後ハンドブレーキをかけます。
次に、シフトレバーをPに入れることで、車が固定され、安全にエンジンを切ることができます。
これにより、誤発進や車の動きを防ぐことができます。
発進時の操作順番は、安全運転に直結するため、正しい手順を身につけることが大切です。
「シフトレバーをDに入れた後にハンドブレーキを解除する」というルールを守ることで、スムーズで安全な発進が可能になります。
車の発進手順をスムーズに覚える方法
- 教習所で習う発進の基本手順
- 路肩からの発進手順と注意点
- 発進時の合図のタイミングと方法
- 停車手順と発進との関連性
- スムーズな発進のための練習方法
教習所で習う発進の基本手順

教習所では、運転の基本として発進手順を細かく指導されます。
これは、正しい操作を身につけることで、安全な発進を確実に行うためです。
発進の基本手順を理解し、しっかりと習得することは、運転をスムーズに行うために欠かせません。
教習所で習う発進の手順は、大きく分けて「準備」「安全確認」「発進操作」の3つのステップに分類されます。
まず、準備として、運転席に座ったらシートとミラーの調整を行い、シートベルトを締めます。
正しい運転姿勢を確保することで、視界が良くなり、スムーズな運転がしやすくなります。
さらに、エンジンをかける前に、ギアがP(パーキング)に入っているかを確認し、ブレーキペダルを踏みながらエンジンを始動させます。
次に、安全確認を行います。
教習所では「ルームミラー→左サイドミラー→右サイドミラー→目視」の順番で確認するよう指導されます。
これは、車の死角をできるだけ減らし、周囲の安全を確保するための重要な手順です。
また、発進の意思を周囲に知らせるために、方向指示器(ウインカー)を右に出します。
この合図を出してから3秒間は進路変更をせずに、安全確認を続けるのが基本とされています。
最後に、発進操作です。
ブレーキペダルを踏んだままシフトレバーをD(ドライブ)に入れ、ハンドブレーキを解除します。
その後、もう一度安全確認を行い、後方や周囲の状況に問題がなければ、ブレーキペダルを徐々に離し、アクセルを軽く踏んで発進します。
教習所では、安全運転の基礎を徹底的に学びます。
この発進手順を確実に身につけることで、教習が終わった後もスムーズな発進ができるようになり、実際の運転時に焦ることなく安全な操作ができるでしょう。
実際に教習所の方が解説している動画はコチラ↓
路肩からの発進手順と注意点

路肩からの発進は、通常の発進よりも安全確認が重要になります。
特に交通量の多い道路では、周囲の車や自転車、歩行者の動きをしっかりと確認しなければなりません。
適切な手順を守ることで、スムーズかつ安全に発進できるため、ここでは具体的な手順と注意点について詳しく解説します。
まず、発進の前に「車両の状態を確認する」ことが重要です。
車が適切に停車しているか、パーキングブレーキ(サイドブレーキ)がかかっているか、シフトレバーがP(パーキング)やN(ニュートラル)になっているかを確認しましょう。
この段階で、シートやミラーの調整も再確認し、運転姿勢が適切であることを確保しておきます。
次に、「周囲の安全確認」を徹底することが求められます。
安全確認の手順としては、まずルームミラーで後方の車両を確認し、次に左サイドミラー、右サイドミラーの順で後続車の位置を把握します。
その後、目視で左後方・右後方の死角を確認し、自転車やバイクが近づいていないか注意しましょう。
ミラーだけでは見えない部分があるため、必ず直接振り返って目視することが大切です。
安全確認が完了したら、「発進の意思を周囲に知らせる」ために右ウインカーを出します。
このとき、ウインカーを出してから3秒以上待ち、後続車に発進の意図を十分に伝えます。
急に発進すると後続車に危険を与えてしまうため、焦らず慎重に動作を行いましょう。
発進する際は、ブレーキペダルを踏みながらシフトレバーをD(ドライブ)に入れ、パーキングブレーキを解除します。
その後、もう一度右サイドミラーと目視で後方確認を行い、車が安全に発進できる状態であることを確認します。
後続車が接近している場合は、無理に発進せず、車の流れが落ち着くのを待つことが大切です。
発進の際は、ブレーキペダルをゆっくり離しながらアクセルを軽く踏み込み、スムーズに車道へ合流します。
このとき、急発進せず、速度を徐々に上げて後続車とスムーズに流れに乗るようにすることがポイントです。
注意点として、路肩から発進する際には「歩行者や自転車に十分注意する」ことが挙げられます。
特に自転車は速度が速く、ミラーに映らない位置から突然現れることがあるため、ミラーと目視の両方で確認する習慣をつけましょう。
また、後続車との距離が十分でない場合は、発進を控え、安全なタイミングを待つことが重要です。
このように、路肩からの発進は通常の発進よりも確認すべき点が多いため、焦らず、慎重に手順を踏むことが安全な運転につながります。
発進時の合図のタイミングと方法

車を発進させる際、正しいタイミングで合図(ウインカー)を出すことは非常に重要です。
合図を適切に行うことで、周囲の車や歩行者に発進の意思を伝え、安全な発進を確保できます。
ここでは、発進時の合図のタイミングと方法について詳しく解説します。
まず、発進の合図は「発進の3秒前」に出すのが基本です。
これは、周囲の車や歩行者に十分な時間を与え、発進することを認識させるためです。
特に交通量の多い道路では、合図が遅れると後続車に危険を与えることがあるため、余裕を持って合図を出すことが求められます。
合図を出す際は、「安全確認を済ませた後」に行うのがポイントです。
発進前にルームミラーやサイドミラーを確認し、後続車の位置を把握した後、右ウインカーを点滅させます。ウインカーを出した後、さらに後方の目視確認を行い、発進の準備を整えます。
また、発進の直前には「再確認」を行うことが大切です。
ウインカーを出してから時間が経つと、後続車の状況が変わることがあるため、発進前に再度ミラーと目視で確認をします。
この段階で、後続車が急接近している場合は、無理に発進せず、安全なタイミングを待つようにしましょう。
発進後は、ウインカーを適切なタイミングで消すことも重要です。
発進が完了し、車が直進状態になったらウインカーをオフにします。ウインカーを長く点灯させたままだと、周囲の車に誤解を与えたり、交通の流れを乱したりする原因になるため、適切なタイミングで消すようにしましょう。
このように、発進時の合図は、適切なタイミングと手順で行うことで、周囲に発進の意思を明確に伝え、安全な運転を実現できます。
停車手順と発進との関連性

停車手順と発進は密接に関連しています。適切な停車を行うことで、発進がスムーズになり、安全性も向上します。
停車時の操作が不十分だと、発進時に戸惑う原因となり、余計なミスを招くことがあるため、停車の際には発進を意識した手順を踏むことが重要です。
まず、停車の基本的な手順を整理すると、次のような流れになります。
- 停止する場所を決める – 停車可能な場所であることを確認し、徐々に減速する。
- 後続車に合図を出す – 方向指示器(ウインカー)やブレーキランプで、停車の意図を周囲に伝える。
- ブレーキペダルを踏み込んで完全停止する – 停車位置が確定したら、ブレーキをしっかり踏んで車を停止させる。
- ハンドブレーキをかける – 車が動かないように、ハンドブレーキを確実にセットする。
- シフトレバーをP(パーキング)に入れる(オートマ車の場合) – ギアを適切な位置に戻して停車状態を維持する。
- エンジンを切る(必要に応じて) – 長時間の停車ではエンジンをオフにする。
この停車手順を確実に実施することで、次に発進する際の操作がシンプルになり、焦ることなくスムーズな動作が可能になります。
例えば、停車時にサイドブレーキを適切に使用していれば、坂道での発進時に車が後退するリスクを軽減できます。
また、シフトレバーをPに入れた状態で停車していれば、誤発進を防ぐことができるでしょう。
一方、停車時の手順を誤ると、発進時に不必要な操作が増えてしまい、スムーズに動き出すことが難しくなります。
たとえば、ウインカーを出さずに停車してしまうと、発進時に周囲の車両へ意図を伝えるのが遅れ、事故のリスクが高まります。
また、シフトレバーの位置を間違えて停車すると、発進時に一度ギアを直す必要が出てきて、スムーズに動き出せません。
発進を円滑に行うためには、停車時に「次にどう発進するのか」を意識することがポイントになります。
停車した場所や車の状態を適切に保つことで、発進時の手順をシンプルにし、安全でスムーズな動作が可能になるのです。
スムーズな発進のための練習方法

発進をスムーズに行うためには、正しい手順を理解するだけでなく、実際に練習を重ねることが大切です。
運転初心者やペーパードライバーの方は、発進時に焦ってしまったり、手順を忘れてしまったりすることがあります。
そのため、実践的な練習を通じて、発進の流れを体で覚えることが重要です。
まず、基本的な発進手順をおさらいしましょう。
- ブレーキを踏みながらエンジンをかける
- シートやミラーの調整、シートベルトの装着を確認する
- シフトレバーをD(ドライブ)に入れる(オートマ車の場合)
- ハンドブレーキを解除する
- 安全確認を行う(ルームミラー→サイドミラー→目視)
- 右ウインカーを出して発進の意思を示す
- 後方の状況を再確認し、ブレーキを緩めながらアクセルを踏む
この一連の流れをスムーズに行うためには、いくつかの練習方法があります。
1. 発進の手順を声に出しながら練習する
初心者にありがちなミスとして、「次に何をすればよいのかわからなくなる」ことがあります。
そのため、発進の手順を声に出しながら操作することで、意識的に手順を整理することができます。
例えば、「ブレーキを踏む、シフトレバーをDにする、ウインカーを出す」と順番に確認しながら練習すると、手順が頭に入りやすくなります。
2. 駐車場などの広い場所で繰り返し発進練習をする
公道での発進はプレッシャーがかかるため、まずは駐車場などの安全な場所で繰り返し練習するのが効果的です。
ブレーキを踏みながらシフトを操作し、発進の流れを何度も試してみることで、手順に慣れることができます。
3. 目視とミラー確認をセットで行う習慣をつける
発進時には、ミラーと目視の両方で安全確認を行うことが重要です。
初心者のうちは、どのタイミングで目視を行えばよいのか迷うことがありますが、「ルームミラー→サイドミラー→目視」という順番を徹底することで、効率よく確認ができます。
これを繰り返すことで、自然と視線の移動が身につき、発進時の安全確認がスムーズに行えるようになります。
4. ブレーキの緩め方を意識する
発進時に急にブレーキを離してしまうと、車がガクンと動き出してしまい、思わぬ危険につながることがあります。
これを防ぐために、ブレーキペダルを「徐々に離す」ことを意識することが大切です。
特にオートマ車では、ブレーキを離すだけで車がゆっくり動き出すクリープ現象があるため、最初はブレーキを軽く緩め、徐々にアクセルを踏み込むことで、スムーズな発進が可能になります。
5. 交通量の少ない時間帯に実際の道路で練習する
発進の手順に慣れてきたら、実際の道路での練習を行いましょう。
交通量の少ない時間帯を選び、発進と停車を繰り返しながら、自信をつけていくことが重要です。
実際の道路では、後続車や歩行者、自転車の動きを意識しながら発進しなければならないため、練習の段階から「周囲の確認」を徹底することがポイントです。
このように、スムーズな発進を行うためには、基本の手順をしっかり覚え、それを反復して練習することが重要です。
最初は難しく感じるかもしれませんが、練習を続けることで、自然と体が動くようになり、スムーズな発進ができるようになるでしょう。
焦らず、自分のペースで確実に技術を身につけることが、安全運転の第一歩となります。
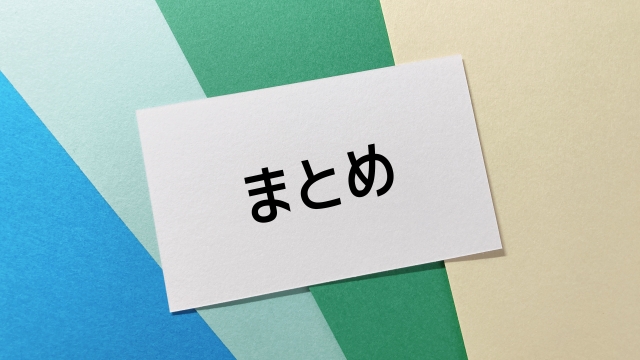
- 発進手順は「準備」「安全確認」「発進操作」の3ステップに分ける
- ブレーキを踏みながらエンジンを始動し、シフトレバーをDに入れる
- サイドブレーキは発進直前に解除するのが正しい手順
- 停車時に正しい手順を踏むことでスムーズな発進につながる
- 発進前の安全確認はミラーと目視を組み合わせる
- 方向指示器(ウインカー)は発進の3秒前に出す
- MT車はクラッチ操作が必要で、半クラッチを意識することが重要
- 路肩から発進する際は、自転車や歩行者の動きを特に注意する
- 発進手順を声に出しながら練習すると覚えやすい
- 広い駐車場で発進の流れを繰り返し練習するのが効果的
- クリープ現象を活用し、急発進を防ぐ意識を持つ
- ブレーキの緩め方を意識するとスムーズな発進ができる
- 教習所では「安全確認→合図→再確認→発進」の流れを重視する
- 発進のシミュレーションを自宅で行うと実践時のミスが減る
- 交通量の少ない時間帯に練習し、実際の道路環境に慣れる
車の発進手順を覚えるには、「準備」「安全確認」「発進操作」の3ステップで整理するとわかりやすくなります。
まず、シートやミラーを調整し、ブレーキを踏みながらエンジンをかけ、シフトレバーをDに入れます。
次に、ルームミラー・サイドミラー・目視で周囲を確認し、発進の3秒前にウインカーを出します。
発進時はブレーキを徐々に離し、アクセルを踏んでスムーズに加速しましょう。
発進をスムーズにするには、声に出して手順を確認したり、駐車場で繰り返し練習するのが効果的です。
特に路肩発進では自転車や歩行者に注意が必要です。焦らず、正しい手順を身につけ、安全な発進を心がけましょう。
以上、この記事が参考になれば幸いです。
 smart-info
smart-info 


