この記事では以下のような悩みにお答えします。
- 前の車がエンジンブレーキを使うと、ブレーキランプがつかず減速に気づきにくくて怖い
- エンジンブレーキの音がうるさく、迷惑に感じることがある
- エンジンブレーキを使っただけなのに煽り運転と誤解されるのではないか不安
エンジンブレーキを適切に使わないと、後続車に不快感を与えたり、交通トラブルの原因になったりすることがあります。
特に、急な減速や大きなエンジン音が発生すると、煽り運転と勘違いされたり、周囲に迷惑をかけたりするリスクがあります。
そのため、エンジンブレーキの正しい使い方を知っておくことが大切です。
そこで、この記事ではエンジンブレーキが「うざい」と思われる理由を解説し、迷惑をかけない使い方や安全運転のポイントを詳しく紹介します。
また、エンジンブレーキが燃費や車体に与える影響、適切な使用方法についても解説し、誤解やトラブルを防ぐためのポイントをお伝えします。
- エンジンブレーキが「うざい」と感じられる理由とその背景
- エンジンブレーキの適切な使い方と注意すべきポイント
- 燃費や車両への影響、デメリットとメリットのバランス
- 煽り運転と誤解されないための運転テクニック

エンジンブレーキは、正しく使えば燃費向上や安全運転に役立つ便利な機能です。しかし、周囲の状況を考えずに乱用すると、後続車に迷惑をかけたり、思わぬトラブルにつながることもあります。適切な使い方を理解し、スマートな運転を心がけましょう。
エンジンブレーキはうざい?迷惑と言われる理由
- うざいと感じる理由とは?
- エンジンブレーキ自体は悪くない!気を付けるポイント
- 燃費は悪くなる?
- なぜうるさい?騒音の原因とは
- エンジンブレーキが煽り運転と勘違いされるケース
- 迷惑行為として通報:Twitterで実際にあった事例
うざいと感じる理由とは?

エンジンブレーキを「うざい」と感じる人がいる理由の多くは、後続車との関係にあります。
特に、エンジンブレーキを使うとブレーキランプが点灯しないため、後続車が減速に気づきにくくなることが問題視されることが多いです。
この状況が続くと、突然車間距離が詰まり、驚いた後続車のドライバーが急ブレーキをかけることになり、結果的に「迷惑だ」「うざい」と感じる要因になってしまいます。
また、エンジンブレーキのかけ方によっては、ギアを急激に落とすことで強い制動力が発生し、後続車が予期しない減速を強いられることもあります。
特に渋滞が発生しやすい市街地や高速道路の合流地点などでは、スムーズな運転が求められるため、不規則な減速は「運転が乱暴」「周囲に配慮が足りない」と捉えられがちです。
さらに、エンジンブレーキを使用する際に発生する「エンジンの唸るような音」も、一部の人には不快に感じられます。
特にスポーツカーやバイクでは、シフトダウン時にエンジン回転数が一気に上がることで大きな音が発生し、周囲のドライバーや歩行者にとって「騒音」として認識されることがあります。
このような理由から、エンジンブレーキの使用が「うざい」と感じられることがあるのです。
しかし、本来エンジンブレーキは燃費向上やブレーキの負担軽減といったメリットがあるため、使い方次第で不満を生じさせることなく活用することが可能です。
エンジンブレーキ自体は悪くない!気を付けるポイント

エンジンブレーキは、クルマを安全に運転するうえで非常に有効な手段です。
しかし、その使い方を誤ると、後続車に不快感を与えたり、思わぬトラブルを招いたりすることがあります。
そのため、エンジンブレーキを適切に使うためのポイントを押さえておくことが大切です。
まず、エンジンブレーキを使用する際に最も気を付けたいのは「後続車との距離」です。
エンジンブレーキはフットブレーキと異なり、ブレーキランプが点灯しないため、後続車が減速に気づきにくくなります。
車間距離が十分に確保されていれば問題ありませんが、詰めすぎている場合は、後続車が急ブレーキをかけざるを得なくなる可能性があるため注意が必要です。
特に交通量の多い道路では、エンジンブレーキだけで減速するのではなく、軽くフットブレーキを踏んでブレーキランプを点灯させることで、後続車に減速の意図を伝えるとよいでしょう。
次に、ギアの操作にも配慮することが大切です。
エンジンブレーキを強くかけようと、いきなり低いギアにシフトダウンすると、エンジン回転数が急激に上がり、車体に負荷がかかります。
これが繰り返されると、エンジンやトランスミッションの寿命を縮めることにもつながるため、段階的にギアを落とすのが望ましい方法です。特にAT車では「L」や「2」などのレンジを適切に使うことで、スムーズに減速できます。
また、エンジンブレーキは長い下り坂での使用が推奨されます。
フットブレーキだけで減速を続けると、ブレーキパッドが過熱し、制動力が低下する「フェード現象」や「ベーパーロック現象」が発生する恐れがあります。このようなトラブルを防ぐためにも、エンジンブレーキとフットブレーキを適切に使い分けることが重要です。
エンジンブレーキは決して悪いものではなく、適切に使えば安全運転に役立つものです。しかし、周囲の状況を考慮しながら、スムーズな運転を心がけることが大切になります。
燃費が悪くなる?

エンジンブレーキを使うと燃費が悪くなるのではないかと考える人もいますが、実際には逆のケースが多いです。
エンジンブレーキを使用することで、燃費を向上させる効果が期待できる場面もあります。
まず、エンジンブレーキの仕組みを理解することが重要です。
エンジンブレーキを使用して減速すると、車はエンジンの抵抗によってスピードを落とします。
このとき、多くの車種では「燃料カット」が行われ、燃料の供給が一時的にストップします。
そのため、アクセルを踏んでいない状態でエンジンブレーキをかけると、ガソリンの消費を抑えることができるのです。
例えば、信号が赤に変わりそうなときに、早めにアクセルを離してエンジンブレーキを活用しながら減速すると、フットブレーキだけで停止するよりも燃費を節約できます。
また、長い下り坂でもエンジンブレーキを使用することで、余分なアクセル操作を減らし、結果的に燃料の無駄遣いを防ぐことができます。
しかし、エンジンブレーキの使い方によっては、逆に燃費が悪化することもあります。
例えば、ギアを頻繁にシフトダウンしすぎると、エンジン回転数が必要以上に上がり、結果として燃料消費が増えることがあります。
また、急激なシフトダウンを繰り返すと、エンジンやトランスミッションに負担がかかるため、車の寿命を縮める原因にもなりかねません。
また、極端にエンジンブレーキだけで減速しようとすると、必要以上に減速することになり、再加速の際に余分な燃料を消費してしまうこともあります。
そのため、エンジンブレーキとフットブレーキを適切に使い分け、状況に応じた運転を心がけることが大切です。
総じて、エンジンブレーキの適切な活用は燃費向上に貢献します。ただし、無闇に多用すると逆効果になる可能性もあるため、運転状況や車の特性を考慮しながら、バランスよく使うことが重要です。
なぜうるさい?騒音の原因とは

エンジンブレーキを使用すると、通常のフットブレーキとは異なり、独特のうなるような音が発生することがあります。
特にスポーツカーやバイク、大型トラックなどでは、その音が大きくなるため、「うるさい」と感じる人が少なくありません。この騒音の原因にはいくつかの要素が関係しています。
まず、エンジンブレーキの仕組みそのものが音の発生に影響を与えています。
エンジンブレーキは、アクセルを離した際にエンジンの回転抵抗を利用して減速する方法です。
このとき、エンジン内部の吸気バルブと排気バルブが急激に変化し、空気の流れが乱れます。
その結果、エンジン内部で「ブォーン」という特徴的な音が発生します。
特に、低いギアにシフトダウンすると、エンジン回転数が一気に上がり、その影響で騒音がより大きくなります。
また、大型車両には「排気ブレーキ(エキゾーストブレーキ)」が搭載されていることが多く、これがさらに音を大きくする要因となっています。
排気ブレーキは、排気ガスの流れを意図的に制限することでエンジンの抵抗を増やし、減速を助ける仕組みですが、この際に「パンッ」「ゴォーッ」といった音が発生します。
特に夜間や住宅街では、この音が響きやすく、近隣住民にとっては騒音と感じられることもあります。
さらに、マフラーの種類によっても音の大きさは変わります。
純正のマフラーは音を抑える構造になっていますが、改造されたスポーツマフラーや直管マフラーでは消音機能が弱くなり、エンジンブレーキをかけた際の音が増幅されます。
このような改造車は特に目立ちやすいため、騒音問題として指摘されることが多いです。
エンジンブレーキの音を抑えるためには、極端なシフトダウンを避けることや、住宅街ではフットブレーキを適度に併用することが有効です。
また、車両の点検を怠らず、排気系の部品が劣化していないか確認することも重要です。
音の問題は、運転する側が気を付けることで軽減できる場合もあるため、周囲の環境を考えた運転を心がけましょう。
エンジンブレーキが煽り運転と勘違いされるケース

エンジンブレーキは、本来安全運転をサポートするための技術ですが、場合によっては煽り運転と誤解されることがあります。
特に、後続車との車間距離が近い場合や、急激な減速をした際にそのように捉えられることが多いです。
エンジンブレーキをかけるとブレーキランプが点灯しないため、後続車のドライバーが減速に気づかず、「いきなりスピードを落とされた」と感じてしまうことがあります。
これが繰り返されると、後続車のドライバーが「意図的に減速して自分を邪魔しているのではないか」と勘違いし、煽り運転と捉える可能性があります。
特に、高速道路や片側一車線の道路では、急な減速が後続車にストレスを与える原因となります。
また、急なシフトダウンによる強いエンジンブレーキを使用すると、車体が不自然に前のめりになり、後続車から見ると「威嚇している」ように見えてしまうこともあります。
意図せずとも、こうした運転が相手に圧力を与える形になり、トラブルの元となることがあるのです。
さらに、エンジンブレーキを多用する場面として、下り坂や信号待ちの前などがありますが、このときに後続車が車間距離を十分に取っていないと、急な減速が危険な動きに見えてしまうことがあります。
特に夜間や悪天候時は視界が悪くなるため、前方車の動きが読みにくく、誤解が生じやすくなります。
このような誤解を避けるためには、フットブレーキを軽く踏んでブレーキランプを点灯させる、急なシフトダウンを避ける、後続車との車間距離を意識するなどの工夫が有効です。
また、万が一、後続車に誤解されて煽り運転を受けそうになった場合は、焦らずに道を譲るか、安全な場所に停車して距離を取ることが重要です。
迷惑行為として通報:Twitterで実際にあった事例
エンジンブレーキを使用したことで「迷惑運転」として通報された事例がTwitterで話題になったことがあります。
この件は、多くのドライバーにとって衝撃的な出来事であり、エンジンブレーキに対する認識の違いが浮き彫りになりました。
実際にTwitterで拡散された事例では、投稿者が通常の走行中にエンジンブレーキを使って減速したところ、後続車が突然警察に通報し、道路上で職務質問を受けたという内容でした。
この投稿が広まると、「エンジンブレーキで通報されるのは理不尽」「車間距離を取らない後続車の方が問題では?」といった意見が相次ぎました。
このようなケースでは、通報した側がエンジンブレーキを「意図的な嫌がらせ」や「急ブレーキ」と誤解した可能性が考えられます。
特に、交通量の多い都市部や高速道路では、前方車両の急な減速に敏感になりやすく、ドライバーが不安を感じた結果、警察に連絡するというケースが発生するのかもしれません。
しかし、エンジンブレーキ自体は違法行為ではなく、適切な方法で使用していれば問題になることはありません。
むしろ、フットブレーキに頼りすぎると、ブレーキパッドが過熱し「フェード現象」や「ベーパーロック現象」が発生する危険があるため、エンジンブレーキを併用することは推奨されています。
こうした誤解を避けるためには、エンジンブレーキを使う際に後続車への配慮を忘れないことが重要です。
例えば、ブレーキランプを点灯させるために軽くフットブレーキを踏む、減速の際にスムーズなシフトダウンを心がけるといった方法が有効です。
また、SNS上で誤った情報が広がることもあるため、エンジンブレーキの正しい使い方についての理解を深めることが、今後のトラブル防止につながるでしょう。
エンジンブレーキはうざい?適切な使い方と注意点
- 使いすぎるとダメ?エンジンや車体への影響
- メリット・デメリットを比較
- 下り坂では使うべき?安全運転のポイント
- エンジンブレーキを使わない人の運転傾向
- オートマ車でも使える?
- 多用すると危険?正しい使い方とコツ
使いすぎるとダメ?エンジンや車体への影響

エンジンブレーキは安全な運転をサポートする便利な機能ですが、使いすぎると車両に負担がかかる可能性があります。
特に、頻繁なシフトダウンや極端な減速を繰り返すと、エンジンやトランスミッションへのダメージにつながることがあります。
まず、エンジンへの影響について考えてみましょう。エンジンブレーキを強くかけるために、急激にギアを下げるとエンジンの回転数が一気に上昇します。
特にMT車(マニュアル車)では、5速から3速、またはそれ以上の極端なシフトダウンを行うと、エンジンの負荷が増大し、内部の部品が過度に摩耗する可能性があります。
これが続くと、エンジンオイルの劣化が早まり、エンジン内部の摩擦が増加して寿命を縮める原因となります。
一方、AT車(オートマチック車)の場合も、適切にギアを切り替えずに「L」や「S」モードを乱用すると、トランスミッション(CVTやAT)の負担が大きくなります。
特にCVT搭載車では、エンジンブレーキを多用しすぎるとベルトやプーリーの摩耗が早まり、修理費用が高額になるケースがあります。
さらに、車体への影響としては、サスペンションや駆動系にも負担がかかることが考えられます。
エンジンブレーキを使いすぎると、エンジンの抵抗力がタイヤに伝わり、タイヤのグリップ力に影響を与えることがあります。
特に雨天時や雪道では、急なエンジンブレーキがタイヤのスリップを引き起こし、制御を失う原因にもなり得ます。
これらの問題を防ぐためには、エンジンブレーキとフットブレーキを適切に併用し、極端なシフトダウンを避けることが重要です。
また、エンジンオイルやトランスミッションフルードの定期的な点検を行うことで、エンジンや駆動系の負担を軽減できます。
エンジンブレーキは便利な機能ですが、適切に使わなければ逆に車両の寿命を縮める可能性があるため、バランスの取れた運転を心がけることが大切です。
メリット・デメリットを比較
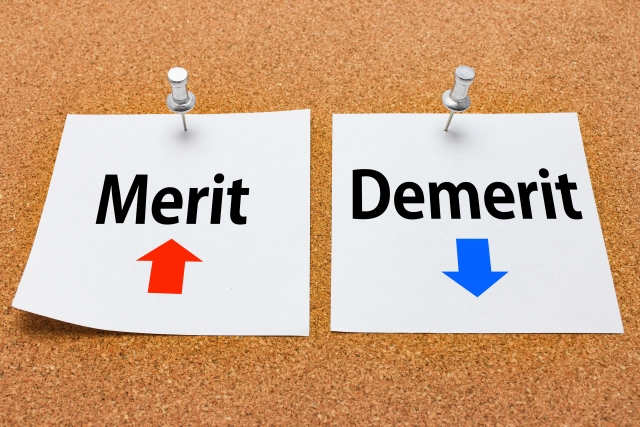
エンジンブレーキは運転の安定性や安全性を高める手段のひとつですが、使い方によってはデメリットが生じることもあります。
ここでは、エンジンブレーキのメリットとデメリットを比較し、それぞれの特徴を詳しく解説します。
メリット
- ブレーキパッドの消耗を抑えられる
フットブレーキだけに頼ると、ブレーキパッドやブレーキローターが摩耗しやすくなります。しかし、エンジンブレーキを適切に併用すれば、フットブレーキの使用頻度を減らすことができ、メンテナンス費用を抑えられます。 - 燃費向上が期待できる
エンジンブレーキを使用すると、多くの車種で燃料供給が一時的にカットされるため、アクセルを踏み続けるよりも燃費が良くなります。特に信号待ちの際や、高速道路のインターチェンジなどで効果を発揮します。 - 長い下り坂での安全性向上
フットブレーキを長時間使用すると、ブレーキが過熱し「フェード現象」や「ベーパーロック現象」を引き起こす可能性があります。エンジンブレーキを使うことで、これらの危険を防ぎ、安全な運転を維持できます。 - 急ブレーキを減らし、スムーズな運転ができる
エンジンブレーキを使いながら減速することで、車の挙動が安定し、同乗者にとっても快適な乗り心地になります。特に渋滞時の「ノロノロ運転」では、エンジンブレーキを活用することで、急なブレーキングを減らせます。
デメリット
- 後続車に減速が伝わりにくい
エンジンブレーキを使用してもブレーキランプが点灯しないため、後続車が気づきにくく、追突事故のリスクが高まることがあります。特に車間距離が短い場合は注意が必要です。 - エンジンやトランスミッションに負担がかかる
極端なシフトダウンや、頻繁なエンジンブレーキの使用は、エンジンやトランスミッションに負荷をかけ、部品の劣化を早める可能性があります。特にCVT車ではトランスミッションの寿命に影響を与えることもあります。 - 極端な使い方をすると車体が不安定になる
エンジンブレーキを強くかけすぎると、駆動輪に強い抵抗がかかり、スリップや挙動の乱れを引き起こす可能性があります。特に路面が滑りやすい状況では、注意が必要です。
エンジンブレーキのメリットを最大限活かすためには、シフトダウンを滑らかに行い、状況に応じてフットブレーキも適切に使うことが重要です。安全運転のために、デメリットも考慮しながら上手に活用しましょう。
下り坂では使うべき?安全運転のポイント

下り坂では、エンジンブレーキを適切に活用することが安全運転につながります。
フットブレーキだけに頼ると、ブレーキシステムに過度な負担がかかり、ブレーキの利きが悪くなる「フェード現象」や「ベーパーロック現象」が発生する恐れがあるためです。
特に長い下り坂では、速度が自然に上がりがちです。
こうした状況でフットブレーキを多用すると、ブレーキパッドが摩耗し、最悪の場合、ブレーキが効かなくなることもあります。
そのため、エンジンブレーキを併用しながらスピードを抑えることが推奨されます。
AT車の場合、「L」や「S」モードに切り替えることでエンジンブレーキを強めることができます。
一般的に、AT車は「D」レンジのままではエンジンブレーキが弱いため、長い下り坂では低いギアを選択し、エンジンの回転抵抗を活かして減速すると良いでしょう。
一方、MT車の場合は、ギアを1段または2段低くして徐々に減速するのが理想的です。
急激にギアを下げるとエンジンに負担がかかるため、スムーズなシフトダウンを心がけることが大切です。
また、下り坂では車間距離を十分に確保し、前方の状況をよく確認しながら運転することも重要です。
万が一、前方の車が急停止した場合に備え、いつでも安全に減速できるように準備しておくことが求められます。
エンジンブレーキを適切に使うことで、ブレーキシステムの負担を軽減し、安全な走行を維持できます。特に長い下り坂では、このテクニックを活用しながら、無理のない運転を心がけることが重要です。
エンジンブレーキを使わない人の運転傾向

エンジンブレーキをほとんど使わずに運転する人には、いくつかの共通した傾向があります。
特に、フットブレーキをメインに使用し、アクセル操作やシフト操作にあまり意識を向けていない人が多い傾向にあります。
このような運転スタイルは、車の操作を簡単にするというメリットがある一方で、車両の負担や安全性の観点からはデメリットも伴います。
まず、エンジンブレーキを使わない人の多くは、「フットブレーキのみで十分に減速できる」と考えています。
AT車が普及している現代では、Dレンジに入れっぱなしで運転する人が多く、ギアを切り替えて減速するという習慣があまり根付いていません。
そのため、速度を落としたいときは、常にブレーキペダルを踏むことで調整するスタイルになりがちです。
また、エンジンブレーキの存在自体を意識していない人も少なくありません。
特に運転初心者やペーパードライバーの中には、教習所でエンジンブレーキの使い方を習ったものの、実際の運転では意識せずにフットブレーキに頼るケースが多いです。
これにより、信号のたびに強めのブレーキをかけたり、下り坂で頻繁にブレーキを踏み続けたりする傾向が見られます。
さらに、エンジンブレーキを使わない人の中には、「車間距離を十分に確保していない」という特徴もあります。
フットブレーキを主に使う人は、前方車の動きをブレーキランプで判断することが多く、車間距離が短めになりがちです。
その結果、急ブレーキを繰り返すことが多くなり、追突のリスクが高まることになります。
このような運転スタイルは、フットブレーキの消耗を早めるだけでなく、燃費の悪化や安全性の低下を招くことがあります。
そのため、エンジンブレーキの活用を意識することで、よりスムーズで安全な運転ができるようになります。
オートマ車でも使える?

エンジンブレーキはMT車(マニュアル車)だけでなく、AT車(オートマ車)でも使うことができます。
ただし、MT車と比べて意識的に操作しなければならない場面が多いため、AT車のエンジンブレーキの使い方を理解しておくことが重要です。
AT車でエンジンブレーキをかける最も簡単な方法は、アクセルペダルを離すことです。
これにより、エンジンの回転抵抗を利用して車の速度を落とすことができます。しかし、この方法では減速効果が弱いため、より強いエンジンブレーキをかける場合は、シフトレンジを切り替える必要があります。
多くのAT車には、「L」「2」「S」「B」などの低速ギアが搭載されています。
例えば、長い下り坂では「L」や「B」にシフトチェンジすることで、エンジンブレーキを強めることができます。
Dレンジのままでは、車が自動的にギアを上げてしまい、エンジンブレーキの効果が弱まるため、適切なタイミングで低速ギアを活用することが大切です。
また、最近のAT車の中には「スポーツモード」や「パドルシフト」が装備されているものもあります。
これらを活用すると、MT車のように任意のタイミングでギアを下げ、エンジンブレーキを利用することが可能になります。
特に高速道路の減速や山道での走行では、パドルシフトを使うことでエンジンブレーキをスムーズに活用できます。
AT車でエンジンブレーキを使う際には、急激なシフトダウンを避けることも重要です。
例えば、Dレンジからいきなり「L」に切り替えると、エンジン回転数が急激に上がり、エンジンやトランスミッションに負担をかける可能性があります。
そのため、徐々にギアを下げることを意識すると、よりスムーズで安全な減速が可能になります。
AT車でも適切にエンジンブレーキを活用することで、ブレーキの負担を軽減し、安全性を向上させることができます。
特に長い下り坂や高速道路の減速時には、フットブレーキと併用して効率的に減速することが推奨されます。
多用すると危険?正しい使い方とコツ

エンジンブレーキは適切に使えば安全運転に役立つ機能ですが、多用しすぎると危険な状況を招くことがあります。
そのため、エンジンブレーキの正しい使い方を理解し、状況に応じて適切に活用することが大切です。
まず、エンジンブレーキを過度に使うと、エンジンやトランスミッションに負担がかかる可能性があります。
特にMT車では、急激に低いギアにシフトダウンすると、エンジン回転数が一気に上がり、エンジン内部の部品に負担がかかります。
また、AT車でも低速ギアを乱用すると、トランスミッションに余計な負荷がかかり、故障のリスクが高まることがあります。
次に、路面状況に応じた使い方が重要です。
例えば、雨の日や雪道では、強いエンジンブレーキをかけると駆動輪がロックし、スリップの原因になります。
特に後輪駆動(FR)車では、リアタイヤが滑りやすくなるため、慎重な操作が求められます。
滑りやすい路面では、急なシフトダウンを避け、フットブレーキと併用しながら緩やかに減速するのが安全です。
さらに、エンジンブレーキを適切に使うためのコツとして、シフトダウンのタイミングが挙げられます。
減速が必要な場面では、いきなりギアを下げるのではなく、少しずつシフトダウンしながら速度を落とすのが理想的です。
例えば、高速道路の出口で減速する際は、早めにアクセルを離し、必要に応じて低速ギアを使うことで、スムーズな減速が可能になります。
また、エンジンブレーキだけに頼るのではなく、フットブレーキと併用することが大切です。
エンジンブレーキだけでは完全に停止することはできないため、最終的にはフットブレーキを使ってしっかりと減速する必要があります。
特に後続車がいる場合は、ブレーキランプが点灯しないと減速に気づかれにくいため、フットブレーキを軽く踏んで後続車に合図を送ることも重要です。
エンジンブレーキは、安全運転をサポートする便利な機能ですが、適切な使い方を守ることが重要です。
多用しすぎず、状況に応じて上手に活用することで、車両への負担を減らしながら、快適で安全な運転を心がけましょう。
エンジンブレーキがうざいと言われる理由と正しい使い方
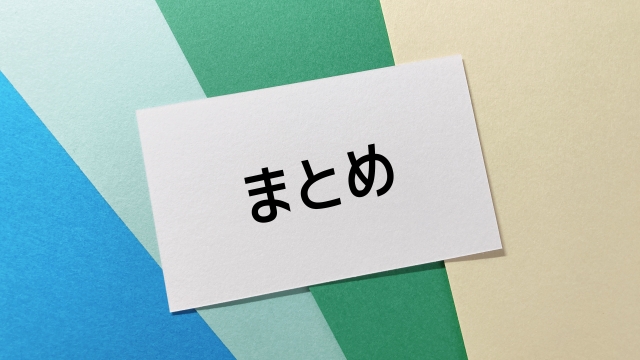
- エンジンブレーキはブレーキランプが点灯しないため、後続車が減速に気づきにくい
- 急なシフトダウンは強い制動力を発生させ、後続車に迷惑をかけることがある
- 特に市街地や渋滞時の不規則な減速は、乱暴な運転と見なされがち
- スポーツカーやバイクのエンジンブレーキは大きな騒音を発生しやすい
- 大型車の排気ブレーキは騒音の原因になり、通報対象になることもある
- エンジンブレーキは煽り運転と誤解されるケースがあり、トラブルにつながることも
- Twitterではエンジンブレーキ使用で通報された事例が話題になったことがある
- 燃費の向上が期待できるが、過度なシフトダウンは燃費を悪化させる可能性もある
- 適切に使えばブレーキパッドの消耗を抑え、メンテナンスコストを削減できる
- 長い下り坂ではエンジンブレーキを使うことで、ブレーキの過熱を防げる
- フットブレーキと併用しながらエンジンブレーキを使うことで、安全な減速が可能
- オートマ車でもLやSモードを活用することでエンジンブレーキを適切に使える
- 多用しすぎるとエンジンやトランスミッションに負担をかけ、車両の寿命を縮める
- 雨天や雪道ではエンジンブレーキの使い方を誤ると、タイヤがスリップしやすくなる
- 車間距離を十分に取ることで、エンジンブレーキの影響を最小限に抑えられる
エンジンブレーキを使うと「うざい」と感じる人がいるのは、ブレーキランプが点灯せず後続車が減速に気づきにくいことや、シフトダウン時の騒音が原因です。
特に急な減速は煽り運転と誤解されることがあるため注意が必要です。
しかし、エンジンブレーキはブレーキの負担軽減や燃費向上に役立つため、正しく使えば安全運転につながります。
長い下り坂ではフットブレーキだけに頼らず、適度にエンジンブレーキを活用することが大切です。
ただし、多用するとエンジンやミッションに負担がかかるため、極端なシフトダウンは避けましょう。
また、後続車への配慮として、軽くフットブレーキを踏みブレーキランプを点灯させる工夫も有効です。
適切な使い方を心がけ、安全運転を意識しましょう。
以上、この記事が参考になれば幸いです。
関連記事
 smart-info
smart-info 



エンジンブレーキの減速を認識出来ないなら、免許証は自主返納した方が良い。また、車間距離をとっていないのでは?フットブレーキを点灯させる必要はない。
エンジンブレーキがウザかったり迷惑だったりする訳ではなく、そう感じたり感じさせる人(人間)が悪いという事。
エンジンブレーキは自然な運転操作で発生するものだが、極端なエンジンブレーキは問題になる場合があり、全く使わない運転も問題があるという事。
結局は、何が言いたいのか分からない。
激しく同意。車間距離が取れてない。前の車しか見ない運転をしてるから(トラックやバスが前なら見えないが)前方の流れが分からない人に迷惑と言われるのが迷惑。警察が言ってたらしい「ブレーキランプで知らせろ」って命令も謎。
バスがフットブレーキだけで長い坂を下って、
ブレーキが効かなくなり、死傷事故起こし、
有罪判決出てますよね。
エンジンブレーキにいちゃもんつける奴は、
車間詰め過ぎで、自動車学校で前の車が突然止まっても安全に止まれるように距離を開けろと習った事すら忘れている。
車間距離の判断もせず、ストップランプの点灯見てるだけ。
速度調節は基本アクセルの調節で行うものだが、
適当にアクセル踏んで一気に加速して、
あおり運転か?と思うくらい近くなると、
パカパカブレーキを踏んでやたらと離れる。
要するに、人として、ドライバーとして、
適性と能力が無い不適格者。
免許返納がふさわしい。
こんなことが記事や話題になっている時点で、この国、終わっていると思う。
また、いくら多様性と言ったって、ここまで思慮の浅い人間にまで(エンブレ時にブレーキランプ灯す)配慮しなければならないのですかね?