こんにちは!smart-info.blogのヒロシです。
車のボンネットやルーフを見て「うわっ!」ってなった経験、ありませんか?
そう、鳥のフンです。
しかも、それを拭き取ったら、塗装がシミになってたり、ひどい時には陥没したり、もう塗装が剥がれてる…。このショック、本当によく分かります。
鳥のフンによる車の塗装剥がれ修理って、どうすればいいのか。
放置してしまったけど大丈夫か、DIYでコンパウンドを使えば直るのか、それともディーラーに修理を頼むべきか、そして費用はいくらかかるのか…。
検索しているあなたは、今まさにそんな不安でいっぱいかもしれませんね。
この記事では、そんな緊急事態に直面したあなたへ、塗装が剥がれてしまった場合のダメージ診断から、DIYでの応急処置、そしてプロに頼む場合の修理代の相場まで、分かりやすく解説していきます。

すぐに修理のやり方や費用を確認したい方はコチラ↓をクリックしてください。
- 鳥のフンがなぜ塗装を溶かすのか、その危険性
- 塗装ダメージの4つのレベルと自己診断法
- DIYでできる修理とプロに任せるべき修理の違い
- 「研磨」と「板金塗装」の費用相場と業者の選び方
鳥のフンによる車の塗装剥がれ修理、まず知るべきこと

「たかがフンでしょ?」って思ってたら、これが大間違い。
鳥のフンは、車の塗装にとって「化学兵器」みたいなものなんです。
まずは敵の恐ろしさと、あなたの車の今の状態を正確に知ることから始めましょう。
ここを間違えると、修理費用が数万円単位で変わってきちゃいますからね。
フンを放置すると危険な理由
「鳥のフンが塗装に悪い」って、なんとなく知ってはいると思うんですが、その「ヤバさ」のレベルは、あなたの想像を絶するかもしれません。
これは単なる「汚れ」ではなく、塗装に対する「化学的な攻撃」そのものなんですよ。
最大の主犯は、フンに含まれる強酸性の「尿酸」です。
鳥は私たちと違って、フンと尿(尿酸)を一緒に排出します。
この尿酸が、車の塗装を保護している一番外側の透明な「クリア層」に対して、即座に化学反応(腐食・浸食)を開始しちゃうんです。
さらに、フンにはタンパク質や消化酵素も含まれています。
これらが分解する過程で、塗装表面を変質させ、頑固な「シミ」や「くすみ」の原因にもなります。
まさに、塗装を破壊するための成分が凝縮された爆弾みたいなものですね。
そして、この化学反応を爆発的に加速させる最悪の触媒が、何を隠そう「熱」なんです。
夏場の炎天下では、車のボンネットやルーフの表面温度は、平気で70℃~80℃以上に達します。
理科の実験を思い出してほしいんですが、化学反応って、温度が高いほどスピードが上がりますよね(一般に温度が10℃上がると反応速度は2倍になるとも言われます)。
熱せられた塗装面の上で、尿酸のクリア層への攻撃力はまさに「激化」します。
これが、夏場だと「数時間」で塗装が致命的なダメージを受ける最大の理由です。
熱が引き起こす「陥没(クレーター)」のメカニズム
熱の恐ろしさは、化学反応の加速だけじゃありません。
フンによる「陥没(クレーター)」の直接的な原因にもなります。
- 膨潤(ぼうじゅん):まず、フンに含まれる水分や酸性成分を塗装面が吸い込み、一時的にふやけて膨れ上がります。
- 急激な収縮:そこへ夏場の直射日光などの「熱」が加わると、膨潤した塗膜から急速に水分が奪われ、フンが乾燥・収縮します。
この「急激な膨潤と収縮」という物理的なストレスが、塗装組織そのものを変形させ、深刻なシワや歪みを引き起こします。
これが、フンの形にくっきりと塗装が凹んでしまう「陥没」の正体です。
冬場であれば24時間放置しても軽度のシミで済むケースでも、夏場の炎天下では、わずか数時間でクリア層を突破し、修復不可能な「陥没」に至る可能性が十分にあるんです。
だからこそ、鳥のフンは「熱」と「時間」との戦いなんですよ。
正しいフンの除去方法と応急処置
もし、あなたの車にまだフンが付着しているなら、絶対に焦って擦ってはいけません!
ここでの対応を間違えると、あなたが自ら「塗装剥がれ」の原因を作ってしまうことになりかねませんからね。
正しい除去方法は、修理費用を数万円単位で節約する、最も重要で簡単な第一歩です。
まず、絶対にやってはいけないNG行動から。これ、やりがちなので本当に注意してください。
これは絶対NG!塗装を破壊する禁止事項
- 乾拭き・ゴシゴシ擦る
ティッシュペーパーや乾いたタオルで擦るのは、もう最悪中の最悪です。鳥は消化のために砂肝に「砂粒」を溜めていることが多く、フンには硬い木の実の殻や砂粒が混じっています。これを乾いたまま擦ることは、目の粗いサンドペーパー(研磨剤)で塗装を擦るのと同じ行為。一瞬でクリア層に無数の「拭き跡(スクラッチ傷)」を刻み込むことになります。 - ワイパーの使用
フロントガラスに付着した場合も、焦ってワイパーを動かさないでください。フンを広範囲に塗り広げて視界を悪化させるだけでなく、酸性成分や油分がワイパーゴムを劣化させ、油膜となって視界を著しく妨げる原因になります。 - 熱湯をかける
「ふやかせばいいんでしょ?」と、沸騰したての熱湯をかけるのもNGです。塗装は急激な温度変化(熱衝撃)に弱く、特に夏場に熱くなったボディに熱湯をかけると、塗装自体にダメージを与えたり、クリア層が浮いたりするリスクがあります。
じゃあ、どうすればいいのか?
鳥のフン除去の鉄則は、ただ一つ。
「徹底的にふやかして、触れるか触れないかの優しさで取る」ことです。
安全・確実!正しいフンの除去手順
手順1:ふやかす(最重要)
カピカピに固着したフンを、塗装にダメージを与えずに取り除くには、まず芯からふやかす必要があります。
- 自宅の場合(ベスト):お湯(塗装への影響を考慮し50℃程度、熱すぎないお風呂くらいが目安)で濡らしたタオルや、厚手のキッチンペーパーを使います。フンの上に「パック」するようにたっぷり水分を含ませて置き、数分間(フンの大きさによる)放置します。
- 外出先の場合(応急処置):ウェットティッシュ(アルコール成分が強すぎないもの)や、コンビニで買った水でティッシュを濡らし、同様にパックします。
- 最強の方法(おすすめ):車に常備しておきたいのが、「鳥フン&虫汚れ除去クリーナー」です。特に泡タイプ(フォームタイプ)のクリーナーは、フンの上に留まって液だれしにくく、クリーミーな泡が汚れを包み込んで効率的にふやかすため、塗装への負担を最小限に抑えられますよ。
手順2:除去する(優しく)
フンが水分を吸って、芯まで十分に柔らかくなったのを確認したら、清潔なウェットティッシュや柔らかいマイクロファイバークロスで、フンを「優しく摘まむように」または「ポンポンと軽く押さえるように」除去します。
この時、絶対に「ベチャっと上から押さえつけて広げない」ことが重要です!
酸性成分を広範囲に塗り広げ、被害を拡大させるのを防ぎます。
ふやけたフンを、塗装面から「浮かせて取る」イメージですね。
手順3:洗浄する(確実に)
フンの固形物を除去した後も、目に見えない酸性成分が塗装面に残っています。
これがシミの原因になるんです。
可能であれば、専用クリーナーや中性のカーシャンプーを使用し、該当箇所を優しく洗浄し、最後にたっぷりの水で成分を完全に洗い流してください。
外出先で水が使えない場合は、新しいウェットティッシュで何度も拭き取り、成分を残さないようにしましょう。
塗装ダメージの4段階診断
フンを安全に除去した後に残った「跡」。これを冷静に、かつ正確に診断することが、今後の修理方針(DIYかプロか)と、その費用を決定づける「トリアージ(緊急度判定)」になります。あなたの車の塗装は、今どのレベルですか?
ステージ1:シミになる
- 症状: 塗装表面に、色の薄いシミが残っている状態。フンが付いていた跡がなんとなく分かる感じです。
- 原因: フンの成分(タンパク質や酸)が塗装表面に固着し、変質させた「ごく初期」の段階です。
- 見分け方: 指で触っても凹凸は感じない。特定の角度から光を当てると見える。爪で軽く擦っても取れない。
- 対処: このレベルなら、まだ望みはあります。市販の専用クリーナーや、水アカ除去剤、軽いコンパウンド(仕上げ用)などで磨けば落ちる可能性があります。塗装の表面(クリア層のごく表層)が変質しているだけなので、その部分を優しく除去すればOKなケースですね。
ステージ2:白く変色する
- 症状: シミが白っぽく濁り、その部分だけ塗装のツヤ(光沢)が明らかに失われている状態。
- 原因: 酸による浸食が、塗装の保護膜である「クリア層」の内部まで到達してしまった状態です。クリア層が化学的に変質し、光が乱反射して白くボケて見えているんですね。
- 見分け方: 触ってもまだ凹凸は感じないか、ごく僅か。しかし、誰が見ても明らかに「そこだけツヤがない」「白ボケしている」のが分かります。
- 対処: クリーナーでの除去は不可能です。クリア層のダメージ部分を物理的に削り取る「コンパウンド(研磨剤)」による研磨作業が必要になります。DIYでも不可能ではありませんが、クリア層を削る作業なので、慎重さが求められます。プロ(カーディテイリング店)の研磨(ポリッシュ)なら、このレベルはほぼ確実に復元可能です。
ステージ3:クレーターになる(陥没)
- 症状: 塗装面がフンの形に明らかに凹んでいる(陥没している)状態。指の腹や爪で触ると、明らかな段差を感じます。
- 原因: 酸がクリア層を突破し、塗装本体の組織を破壊。さらに、第1章で解説した「膨潤と収縮」のプロセスにより、塗膜自体が物理的に変形・収縮してしまった状態です。
- 見分け方:浅い陥没: 指の腹でなぞると凹みを感じるが、爪が「ガリッ」とは引っかからないレベル。深い陥没: 爪でなぞると、明らかに「ガリガリッ」と引っかかるレベル。
- 対処: ここがDIYとプロの分岐点です。「浅い陥没」であれば、プロによる「重研磨」(強めの研磨)で、周囲の塗装を削り込み、段差を目立たなくできる可能性があります。ただし、完全に平滑に戻るかは五分五分です。DIYでの研磨は、まず無理(悪化させるリスク大)と考えた方がいいでしょう。
「深い陥没」の場合、研磨ではもはや回復不可能です。削っても凹みは消えません。このレベルは「板金塗装(再塗装)」が必要となります。
ステージ4:車の塗装が剥がれて錆になる
- 症状: 塗装が水ぶくれのようにプクッと浮き上がり、やがてパリパリと剥がれている。下地の金属(鋼板)が露出し、赤茶色のサビ(錆)が発生している。
- 原因: 塗装が完全に腐食し、ボディの鋼板までダメージが達した「末期症状」です。塗装の構造は、下から「鋼板 → 下地 → カラー層 → クリア層」となっていますが、そのすべてが酸によって破壊され尽くした状態です。
- 見分け方: 見たままです。塗装が剥がれ、金属が見えたり、サビが出ている。
- 対処: DIYでの修復は絶対に不可能です。これを放置すると、サビが鋼板の内部へと侵食し、やがて穴が開き、ボンネットやドア、ルーフといったパネル自体の交換が必要となり、極めて高額な修理費用(数十万円)が発生します。即刻、「板金塗装」による再塗装が必須となります。
「塗装剥がれ」で検索したあなたへ
もし、あなたが「塗装剥がれ」というキーワードでこの記事にたどり着いたのなら、あなたの愛車はステージ4の緊急事態である可能性が極めて高いです。
コンパウンドでどうにかなるレベルではありません。
一刻も早くサビの進行を食い止め、修理費用を最小限に抑えるため、今すぐこの記事の「板金塗装」のセクションを読み進め、専門業者への相談準備を始めてください!
DIYでのコンパウンド修理法
もし、あなたの車のダメージがステージ2(白く変色)、またはステージ3でも「ごくごく浅い陥没(爪が全く引っかからないレベル)」であれば、DIYでコンパウンド(研磨剤)を使用して研磨し、目立たなくできる可能性があります。
ただし!コンパウンドは「傷を消す魔法のクリーム」じゃありません。
その正体は「研磨剤」、つまり微細なヤスリです。
ダメージ部分の周囲のクリア層を削り、段差を滑らかにすることで傷やシミを目立たなくする技術なんです。
ですから、使えば必ず塗装のクリア層は薄くなります。この大前提を絶対に忘れないでください。
DIYでのコンパウンド作業は、諸刃の剣。うまくいけば数千円で悩みが解決しますが、失敗すれば数万円の「再塗装」が確定する、ハイリスクな作業でもあるんですよ。
コンパウンドの種類と選び方
コンパウンドには、削る力の強さ(粒子の粗さ)によって種類があります。
- 粗目・中目: 削る力が強い。深い傷用ですが、素人が使うと「磨き傷」がひどくなり、まず収拾がつかなくなります。今回は絶対NG。
- 細目: 浅い傷や、ステージ2の白ボケに使うかどうか、というレベル。
- 極細・仕上げ用: 粒子が非常に細かい。最終的なツヤ出しや、ごく浅いシミ(ステージ1~2)に使います。
初心者のDIYでは、必ず「極細」や「仕上げ用」といった最も粒子の細かい(目の細かい)タイプから試すのが鉄則です。
いきなり粗いコンパウンドを使うと、そのコンパウンドによる「磨き傷」が残り、それを消すためにさらに細かいコンパウンドが必要になり…と、泥沼にはまりますよ。
DIYコンパウンド作業の(簡単な)手順
もし挑戦するなら、以下の手順を「慎重すぎるほど慎重に」進めてください。
- 完全な洗車: ボディに砂や鉄粉が残ったまま作業すると、それを引きずってボディ全体に新たな研磨傷(スクラッチ)を広げることになります。洗車は完璧に行ってください。
- マスキング: 磨く箇所の周囲(特にゴムや樹脂パーツ)をマスキングテープで保護(養生)します。コンパウンドが付くと白く変色して取れなくなります。
- 研磨(極細から): まずは「極細」コンパウンドを専用のスポンジに少量(あずき粒程度)つけます。そして、10cm四方くらいの「狭い範囲」を、力を入れずに「直線的に」優しく磨きます。(円を描くように磨くとムラになりやすいです)。
- 拭き取りと確認: 磨いたら、すぐにコンパウンドをキレイなマイクロファイバークロスで拭き取ります。力を入れてゴシゴシ拭かないこと。
- 状態確認: 様々な角度から光を当てて、シミや白ボケが消えたか、変な磨き傷がついていないか確認します。
もし「極細」で消えなければ? …正直、私ならその時点で「DIYの限界」と判断し、プロに任せることを推奨します。
ここで「細目」に手を出すと、前述の「磨きすぎ」リスクが一気に高まりますからね。
コンパウンドDIYの最大の注意点
一番の注意点は、「やり過ぎ厳禁」、これに尽きます。
塗装(クリア層)は無限ではありません。
国産車だと、その厚みはわずか30~50ミクロン(0.03~0.05mm)、食品用ラップフィルムより薄いんです。
コンパウンドで削れる量は、そのうちの本当にごく僅か。
「シミが消えない!」とムキになって同じ場所をゴシゴシ磨き続けると、あっという間にクリア層が削り取られ、下の「カラー層」が露出してしまいます。
これを「塗装を剥がす」と言います。
一度カラー層が露出したら、もうコンパウンドでは元に戻りません。
修理方法は「板金塗装(再塗装)」のみとなり、修理費用は数万円に跳ね上がります。
シミを消そうとして、もっと高額な修理を確定させてしまう…これだけは絶対に避けてくださいね。
DIY修理が不可能なレベルとは?
DIYでのコンパウンド修理法について解説しましたが、はっきり言います。
ステージ4、つまり「塗装が剥がれて、下地の金属が見えている」状態は、DIYでの修復は不可能です。
なぜなら、何度も言うようにコンパウンドは「削る」道具。
でも、ステージ4は塗装が「失われている」状態ですよね。無いものをいくら削っても、元には戻りません。これはもう、DIYの域を完全に超えています。
また、ステージ3の「クレーター(陥没)」でも、爪が明らかに「ガリッ」と引っかかるほど深いものは、DIYでコンパウンドをかけてもまず取れません。
それどころか、陥没の周りの正常な塗装だけが削れていき、陥没のフチがなだらかになることで、かえって「すり鉢状」に凹みが目立ってしまい、失敗するケースがほとんどです。
サビが見えたらDIYは絶対NG
特に「塗装剥がれ」によって赤茶色の「サビ」が見えてしまっている場合。
これはもう、市販のサビ取り剤やタッチペンでどうにかなるレベルではありません。
サビというのは、水面に浮かぶ氷山の一角のようなもの。
表面に見えているサビ(点)は小さくても、塗装の下、鋼板の内部では、見えないところで(面で)侵食が広がっていることがほとんどなんです。
市販のサビ転換剤(赤サビを黒サビに変えて進行を止める薬剤)もありますが、あれはあくまで一時しのぎ。プロの板金塗装で行う「ケレン作業」(サビを物理的に完全に削り取る作業)と「防錆処理」を根本から行わない限り、内部に残ったサビは水分と反応し、数ヶ月後には塗装を内側から押し上げて、必ず再発します。
応急処置としての「タッチペン」という選択
「じゃあ、サビが出たら何もできないのか?」…そんな時の「応急処置」として「タッチペン(タッチアップペイント)」があります。
ただし、これは「修理」ではなく、あくまで本格的な板金塗装に出すまでの間、サビの進行を食い止め、ダメージの拡大を防ぐための「一時しのぎ」だと割り切ってください。
美観の回復は一切期待できません。
むしろ、塗った部分が凹凸になったり、色が微妙に違ったりして、確実に「修理跡」として目立ちます。
タッチペンでの応急処置(簡易手順)
もし「本格修理までの数日間、どうしてもサビの進行を止めたい」というなら、以下の手順で行います。
- サビ取り: 剥がれた部分の赤サビを、サンドペーパー(600番~1000番程度)で完全に削り落とします。サビが残っていると、上から塗っても意味がありません。
- 脱脂: シリコンオフ(脱脂剤)で、削った部分の油分や汚れを徹底的に拭き取ります。これをしないと塗料が密着しません。
- 塗布: ボディカラーと同色のタッチペンを、「点を置くように」ちょんちょんと塗ります。一気に塗ろうとせず、乾燥させながら薄く重ねるのがコツです。
繰り返しますが、これは美観を損なう「応急処置」です。
このレベルになったら、失われた塗装を新たに「足す(=再塗装)」しかありません。
サビが鋼板を突き破って穴が開く前に、プロの「板金塗装」を検討する段階ですよ。
鳥のフンで車の塗装剥がれ修理、費用と業者の選び方

さて、ここからが本題かもしれませんね。
DIYが無理なレベルのダメージ(ステージ3の深い陥没やステージ4の塗装剥がれ)をプロに直してもらう場合、一体いくらかかるのか。
そして、どこに頼むのがベストなのか。ここ、一番気になりますよね。
まず大前提として、あなたの車のダメージレベルによって「行くべきお店」が根本的に違います。
- ステージ2~3(シミ・浅い陥没): 修理は「研磨(ポリッシュ)」。依頼先は「カーディテイリング店」です。
- ステージ4(塗装剥がれ・サビ): 修理は「再塗装(板金塗装)」。依頼先は「板金塗装工場」や「ディーラー」です。
この2つは、似ているようで全く違うサービスなので、間違えないようにしましょうね。
陥没やシミを消す研磨の費用
まず、ダメージがステージ2~3(シミ・浅い陥没)で、「再塗装」までは必要ないけど、DIYじゃ取れない…という場合。
これは「板金塗装工場」ではなく、「カーディテイリング店(コーティング専門店など)」の「研磨(ポリッシュ)」サービスになります。
これは塗装を剥がすことなく、塗装の表面(クリア層)のダメージ層だけを、専用の機材(ポリッシャー)と数十種類のコンパウンド、バフ(研磨用のスポンジやウール)を使い分けて精密に削り取り、平滑にして塗装本来の輝きを復元する専門技術です。
プロに「研磨」を頼むメリット
DIYのコンパウンド作業との最大の違いは、その「精度」と「安全性」です。
プロは、まず「膜厚計(まくあつけい)」という機械で、塗装の厚み(ミクロン単位)を測定します。
その車の塗装がどれくらい残っているかを把握した上で、「あと何ミクロンまでなら安全に削れるか」を計算しながら作業するんです。
素人の手磨きと違って、専用のポリッシャー(研磨機械)で均一に磨き上げるため、磨きムラも発生しません。
DIYで失敗してクリア層を剥がしてしまうリスクを考えれば、ステージ2以上のダメージは、最初から「磨き」の専門家であるカーディテイリング店に任せるのが、結果的に一番安上がりになるケースも多いですよ。
研磨費用が変わる理由
研磨の費用は、主に以下の要因で決まってきます。
- 車のサイズ: S, M, L, LLなど、面積が広くなれば当然高くなります。
- 塗装の色: 黒や紺、赤といった濃色車は、シミや磨き傷が非常に目立ちやすいため、作業が格段にシビアになります。そのため、淡色車(白やシルバー)よりも高額になるのが一般的です。
- ダメージの深さ: ステージ2の白ボケ程度なら軽研磨(ライトポリッシュ)で済みますが、ステージ3の陥没となると重研磨(ハードポリッシュ)が必要になり、手間がかかる分、高くなります。

費用はあくまで目安ですが、こんな感じです。
| サービス名 | 内容 | 料金目安 (税込) |
|---|---|---|
| 部分キズ取り研磨 | 5cm x 5cm程度のピンポイントなシミ・陥没 | 1箇所 ¥3,000~¥8,000程度 |
| スタンダードポリッシュ | 中程度の陥没(クレーター)除去(パネル全体) | Mサイズ (プリウス等): 約 ¥29,000~¥50,000 |
| スペシャルポリッシュ | 重度のシミ・陥没除去(パネル全体) | Mサイズ (プリウス等): 約 ¥66,000~¥100,000 |
※上記はあくまで一般的な目安です。お店や車の状態、研磨のレベル(どこまで完璧を求めるか)によって大きく異なります。
ただ、プロでも「深すぎるクレーター(ステージ3の深い陥没)は研磨では取り切れない」と明言していることが多いです。その場合は、次の「板金塗装」の領域になります。
剥がれの板金塗装、修理代相場

そして、ステージ4「塗装剥がれ」や、研磨ではどうにもならない「重度の陥没」を直す、唯一の本格修理が「板金塗装(再塗装)」です。
これは「磨く」のではなく、古い塗装を剥がし、下地から作り直して「塗り直す」作業になります。
鳥のフン被害は、ボンネットやルーフといった「水平なパネル」に集中します。
ここは太陽光で熱ダメージが加速しやすく、しかも面積が広くて修理が難しいため、費用が高額になりやすい、という最悪のコンボなんです。
なぜボンネットやルーフの修理が難しいかというと、人間の目は「水平な面」の色の違いやムラに最も敏感だからです。
小さな剥がれだからと「部分塗装(スポットリペア)」で境目をぼかした場合、その「ぼかし」が角度によって見えてしまい、いかにも「修理しました」という跡が目立ちやすいんですよ。
このため、ボンネットやルーフに落ちた直径5cmのフン跡(塗装剥がれ)を完璧に修理するために、パネル全面を塗り直す「1本塗装(パネル塗装)」が必要になるケースは、決して珍しくありません。
板金塗装って何をするの?
板金塗装の工程は、非常に複雑です。(出典:関西ペイント『自動車補修用塗料とは』)
- 旧塗膜の剥離・サビ取り: まず、ダメージ部分の古い塗装とサビを、サンダーなどで完全に削り落とします(ケレン作業)。
- パテ盛り: 陥没やサビで凹んだ部分に、粘土のような「パテ」を盛り、乾燥後に研磨して元のパネルの形状を復元します。
- 下地処理(サフェーサー): パテの上から「サフェーサー」という下地塗料を吹き付けます。これは、パテが塗料を吸い込むのを防ぎ、上塗り塗料の密着性を高め、防錆効果も持つ重要な層です。
- 調色(最重要): 車の既存の塗装(新車時から紫外線などで微妙に色褪せている)と、新しく塗る塗料の色を完璧に合わせる「調色」作業。職人の腕が最も問われる部分です。
- 塗装・乾燥: 塗装ブースというゴミやホコリが入らない専用の部屋で、色(カラーベース)、透明な保護層(クリアコート)の順にスプレーガンで吹き付け、加熱乾燥させます。
- 磨き: 最後に、塗装面の細かなブツ(ゴミ)や「ゆず肌」と呼ばれる凹凸をコンパウンドで磨き上げ、ツヤを出して完成です。
これだけの工程が必要なので、どうしても費用は高額になってしまいます。
| 修理箇所 (パネル) | 修理内容 | 費用相場(目安) |
|---|---|---|
| 部分塗装 | 20cm x 20cm程度の剥がれ・サビ修理 | ¥11,000 ~ ¥14,000 (普通車) |
| サビ修理 (軽度) | 表面のサビ除去・防錆処理 | ¥5,000 ~ ¥30,000 (塗装代別途) |
| ルーフ (1本塗装) | パネル全体の再塗装(軽度の損傷) | ¥30,000 ~ ¥50,000 |
| ボンネット (1本塗装) | パネル全体の再塗装(軽度の損傷) | ¥50,000程度 |
| サビ修理 (穴あき) | 鋼板の穴あき(重度) | ¥10,000 ~ ¥50,000 (1箇所・塗装代別途) |
※費用は、ソリッド(単色)の価格です。メタリックやパール、3コートパールといった特殊な塗装は、調色や塗装工程が複雑になるため、1.2倍~1.5倍程度、高額になります。
サビを放置すると高額に!
最重要なので繰り返します。塗装が剥がれて金属が露出し、サビが発生している場合、上記の塗装代に「サビ修理代」が別途加算されます。
もしサビを放置しすぎて鋼板に穴が開いてしまったら…もう最悪です。溶接や鋼板の切り貼りといった「板金」作業が必要になり、修理代は一気に跳ね上がります。最悪、パネル自体の交換となり、ボンネットやルーフの交換は10万円を優に超えてきますよ…。
修理業者はディーラー?工場?
「塗装剥がれ」の本格修理(板金塗装)を依頼する先は、主にこの4つですが、今回の「シビアな塗装剥がれ修理」という観点で見ると、特徴が大きく分かれます。
1. ディーラー
メリット: メーカーの看板を背負っている「絶対的な安心感」が最大のメリットです。メーカー基準の作業品質がマニュアル化されており、純正塗料の使用など、仕上がりのクオリティは間違いなく高いレベルで安定しています。修理後の保証もしっかりしていることが多いですね。
デメリット: 「費用の高額さ」です。ディーラーには自社で板金塗装工場を持っている所もありますが、多くは提携する優良な「下請けの板金塗装工場」に作業を外注しています。そのため、工場の見積もりにディーラーの「中間マージン」が上乗せされるため、費用は4つの中で最も高額になる傾向があります。
2. 板金塗装工場
メリット: 塗装と修復の専門技術者が在籍する「職人の店」です。ディーラーからの下請け作業も行うような高い技術力を持つ優良な工場も多く、そうした工場に直接依頼することで、中間マージンを排した「適正価格」での修理が期待できます。コストと品質のバランスが最も良い選択肢と言えるかもしれません。
デメリット: 「工場によって技術力や設備に大きな差がある」ことです。腕の悪い工場に当たると、色が合っていなかったり、数年後にパテが痩せて(凹んで)きたり…といったトラブルも。信頼できる優良な工場を自力で見つける「目利き」が必要になります。
良い板金塗装工場の見分け方(ヒント)
- 塗装ブースの有無: ゴミやホコリをシャットアウトする「専用の塗装ブース」があるか。これが無いと、塗装面にゴミが付着(ブツ)しやすく、仕上がりに大きく影響します。
- 見積もりの丁寧さ: 車をしっかり見て、「なぜこの作業が必要か」「なぜこの金額になるか」を素人にも分かるように説明してくれる工場は信頼できる可能性が高いです。
- 施工例の写真: 過去の修理実績(ビフォーアフター)を写真などで見せてくれるか、なども参考になりますね。
3. カー用品店 / 4. ガソリンスタンド
メリット: 全国展開しており、アクセスしやすく手軽に見積もり・依頼ができるのが強みです。
デメリット: これらの店舗の多くは、バンパーの擦り傷やドアノブの引っかき傷といった「簡易的なキズ修理(リペア)」を得意としています。鳥のフンによる「塗装剥がれ」のような、下地処理やサビ取り、シビアな調色が求められる「本格的な板金塗装(レストア)」は、専門外である可能性が高いです。特にボンネットやルーフの1本塗装は、設備や技術者の問題で対応できないか、結局は下請けの工場に回すことになるケースが多いかなと思います。
結論としては、今回の「塗装剥がれ」(ステージ4)の本格的な修理を依頼するならば、「費用は高くても安心感を最優先するならディーラー」、「コストと品質の両立を自分で探求するなら優良な板金塗装工場」の2択かな、と私は思いますよ。
塗装剥がれを予防するコーティング
1回のフン被害で、ボンネットの再塗装に ¥50,000…。こんな悲劇、二度と繰り返したくないですよね。この苦い経験(あるいは、寸前だった経験)をしたあなたなら、再発防止の重要性を誰よりも理解しているはずです。
ここでの予防策は、単なるメンテナンスではなく、将来の数万円の出費を回避するための「最も確実な投資」と言えます。優先度順に解説しますね。
優先度【高】:駐車環境の最適化(最も重要)
これが一番効果的で、根本的な対策です。鳥のフン被害のリスクを物理的にゼロに近づける方法ですね。
- 避けるべき場所: 「電線の下」「街路樹の下」。これらは鳥が休息し、営巣する「ホットスポット」です。ここに停めるのは「どうぞフンを落としてください」と言っているようなもの。
- 選ぶべき場所: 「屋根付きの場所(カーポート、ガレージ)」。これが最強の対策であることは言うまでもありません。鳥から車を物理的に完全に隠します。
- 意外な対策: 屋根付きが無理なら、「人通りの多い場所」や「店舗の入り口前」など、鳥が警戒して近づきにくい場所を選ぶのも、地味に効果があったりします。
優先度【中】:物理的防御(カーカバー)
屋根付きの駐車場を確保できない場合、最も確実な次善策は「ボディカバーをかける」ことです。
メリット: カバーはフン汚れを直接防ぐだけでなく、酸性成分が塗装に浸透することも完全に防ぎます。フン以外にも、酸性雨、黄砂、紫外線のダメージからも塗装を守ってくれる万能選手です。
デメリット: やはり「着脱の手間」ですよね。毎日車に乗る人には現実的ではないかもしれません。また、風が強い日にカバーがバタつくと、カバーとボディの間に入り込んだ砂埃で塗装に擦り傷がつくリスクもあります。車体が汚れたままカバーをかけるのもNGですね。
優先度【低】:化学的防御(コーティング)
そして、車の塗装の身代わりとなる「犠牲層」を作る対策が、ガラスコーティングなどのボディコーティングです。
コーティング施工車は、汚れが塗装に直接付着するのを防ぎ、酸の浸透を「遅らせる」ことができます。ここ、重要なので繰り返しますが、「防ぐ」のではなく「遅らせる」です。
ここで、多くの人が勘違いしている重要な認識の転換が必要です。
コーティングは「無敵シールド」じゃない!「時間稼ぎ」だ!
高価なガラスコーティングを施工したからといって、「もうフンが付いても大丈夫」なんてことは絶対にありません。コーティングは「無敵のシールド」ではなく、あくまで「時間を稼ぐためのバッファー(緩衝材)」です。
強酸性のフンは、そのコーティング層自体も、塗装と同じように劣化させ、ダメージを与えます。
コーティングの真の価値は、塗装を無敵にすることではなく、
- 塗装の「身代わり」となって、フンの第一撃を受け止めてくれること。
- それによって、ドライバーがフンに気づき、安全に除去するまでの「猶予時間」を、未施工車の「数時間」から「1日~2日」へと劇的に伸ばしてくれること。
- フンが固着しにくく、水洗いやクリーナーで「安全に除去しやすく」なること。
この3点にあります。したがって、コーティング施工車であっても、「フンが付着したら、できるだけ早く除去する」という鉄則は、まったく変わりませんよ!放置すれば、コーティング層が破壊され、結局その下の塗装までダメージが達してしまいますからね。
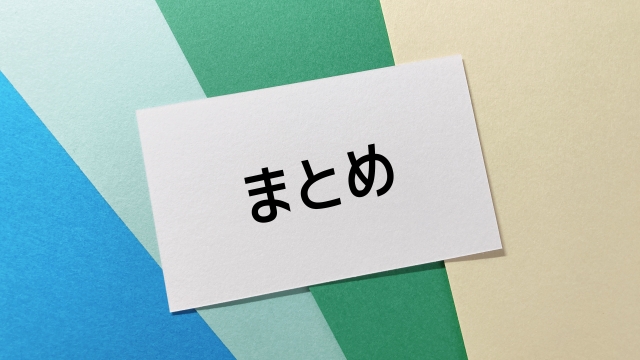
ここまで、本当にお疲れ様でした。鳥のフンによる車の塗装ダメージは、その発見から対応までの「時間」と、環境要因である「熱」との戦いである、ということがお分かりいただけたかなと思います。
「できるだけ早く、かつ安全に除去すること」
これが、数千円から数万円の修理費用を節約する、唯一にして最大の方法です。
もし、あなたの愛車にダメージがすでに発生してしまっている場合は、パニックにならず、本記事の「4段階ダメージ診断」をもう一度見返して、冷静に現状を分析してください。
- ステージ1(シミ): DIYでクリーナーや水アカ除去剤に挑戦。
- ステージ2(白ボケ): DIYで「極細」コンパウンドに挑戦するか、無理せず「カーディテイリング店」に「研磨(ポリッシュ)」を依頼。
- ステージ3(陥没): DIYは諦める。「浅い」ならカーディテイリング店の「重研磨」で目立たなくなる可能性あり。「深い」なら「板金塗装」一択。
- ステージ4(塗装剥がれ・サビ): 最緊急事態。DIYは絶対不可能。タッチペンは応急処置。一刻も早く「板金塗装工場」か「ディーラー」で本格的な塗装修理の見積もりを!
「塗装剥がれ」を放置する最大のリスクは、なんといっても「サビ(錆)」です。
サビは鋼板の「ガン細胞」のようなもの。一度発生すると、塗装の下で、目に見えないところで静かに、しかし確実に進行し、鋼板を蝕んでいきます。
サビが鋼板を突き破って穴が開いてしまうと、修理費用が跳ね上がるだけでなく、車の「資産価値」は大きく下落します。さらに、モノコックボディの車では、ボディパネルも車全体の強度を担う重要な構造部材。サビによる強度低下は、万が一の事故の際の「安全性」にも関わってくる、非常に深刻な問題なんですよ。
この記事で紹介した費用や修理方法は、あくまで一般的な目安です。あなたの愛車の塗装の状態、車種、色(メタリックやパールは高い)、サビの進行度合いによって、費用は一台一台まったく違ってきます。
「これくらいなら大丈夫かな…」と自己判断で放置するのが、一番危険です。
手遅れになって、「あの時すぐに相談していれば…」と数十万円の修理代に泣く前に、まずは信頼できる専門業者(板金塗装工場やディーラー)に実車を見せて、正確な診断と見積もりをしてもらうこと。
できれば1社だけでなく、ディーラーと板金塗装工場の両方で「相見積もり」を取ってみることを強くおすすめします。修理方法や金額を比較検討し、あなたが納得できるところで修理を依頼してくださいね。
この記事が、あなたの愛車を最悪の事態から救うための一助になれば、私(ヒロシ)としてもうれしい限りです!
 smart-info
smart-info 


