こんにちは!smart-info.blogのヒロシです。
ドライブから帰ってきたら、車の前側が虫だらけ…なんてこと、ありますよね。
特に夜間の高速道路を走った後とか、もう最悪です。
これをすぐにでも落としたいけど、専用クリーナーがない時、「車の虫取りは家にあるもの」で何とかならないかな?って考えると思います。
食器用洗剤とか、掃除で使う重曹、アルコールスプレーなんかが頭に浮かぶかもしれません。
でも、ちょっと待ってください!
家にあるもので対処しようとして、もし塗装をダメにしてしまったら…?
実は、虫の汚れって放置すると塗装を溶かす厄介なもので、落とし方を間違えると取り返しのつかないシミになることもあるんですよ。
この記事では、家にあるもので安全に対処できる方法から、激落ちくん(メラミンスポンジ)や漂白剤など、絶対に使っちゃダメなアイテムまで、詳しく解説していきますね。
- 家にあるもので安全な虫取り方法2選
- 車の塗装を破壊する絶対NGなアイテム5つ
- 塗装を傷つけない虫汚れの正しい落とし方
- 虫汚れをシミにしないための予防策
車の虫取りに家にあるものを使う危険性
「家にあるもの」でパパっと掃除したい気持ち、すごく分かります。
でも、車の塗装って私たちが思っているよりずっとデリケートなんですよ。
使うものを間違えると、虫汚れは落としちゃったけど、塗装が傷だらけでツヤがなくなった…なんてことになりかねません。
まずは、何がOKで何がNGなのか、その科学的な理由もしっかり見ていきましょう。
安全なのはお湯と食器用洗剤
まず、結論から。
家にあるもので「条件付き」で使えるのは、「お湯」と「中性の食器用洗剤」の2つだけです。
ただ、これらは本当に、「付着したばかりの軽い汚れ」に対する応急処置だと考えてください。
万能ではありませんし、デメリットもあります。過度な期待は禁物ですよ。
お湯(60〜80℃)
家にあるもので、最も安全かつ塗装にダメージを与えない方法が「お湯」です。
これは洗剤のように化学的に汚れを「分解」するのではなく、物理的に汚れを「ふやかす」のが目的です。
なぜお湯が有効かというと、虫の死骸の主成分である「タンパク質」と「油脂」は、熱によって柔らかくなる性質(タンパク質の熱変性)があるからです。
カチカチに乾燥してこびりついた汚れも、熱いお湯で温められると、ふにゃふにゃとふやけて塗装から剥がれやすくなります。
具体的な使い方は、まず60〜80℃のお湯を用意します。給湯器の温度設定でOKですね。これを虫が付着している箇所にゆっくりと、広範囲にかけ流します。

より効果的なのは「お湯湿布(パック)」です。
厚手のタオルやキッチンペーパーをお湯に浸し、火傷に十分注意しながら軽く絞って、虫の死骸の上に3〜5分ほど置いてパックします。
こうすることで熱がじっくりと伝わり、より効果的に汚れをふやかすことができますよ。
ただし、お湯にも限界があります。これはあくまで「ふやかす」作業。
すでに塗装に侵食して「シミ」になってしまった跡は、お湯ではどうにもなりません。
熱湯(100℃)は絶対にNG!
「熱いほど効果がある」と考えるのは危険です。
沸騰した熱湯をかけると、塗装面と、その下にある鉄板や樹脂(バンパー)との「熱膨張率の違い」から、急激な温度変化に耐えられず、塗装にヒビが入ったり(クラック)、樹脂パーツが変形したりするリスクがあります。
また、窓ガラスにかかると割れる危険性も。60〜80℃の「触れないけど沸騰はしていない」温度がベストですよ。
食器用洗剤(中性)
もう一つの選択肢が、キッチンの「食器用洗剤」です。
これも条件付きで使えます。
まず、必ず「中性」の洗剤を選んでください。
製品の裏側に「液性:中性」と書いてあることを確認しましょう。
「弱アルカリ性」や「酸性」、あるいは漂白成分入りのものは、塗装やコーティングにダメージを与えるため絶対NGです。
中性洗剤に含まれる「界面活性剤」が、虫の死骸に含まれる「油脂」を分解し、水と混ざり合う状態(乳化)にして、汚れを浮かせる効果があります。
使い方は、原液をそのままボディに塗布するのは絶対にダメです。
洗車用バケツなどで、水またはぬるま湯で数十倍〜数百倍にしっかりと希釈し、スポンジでよく泡立てます。
その泡を虫の付着箇所に乗せ、数分間放置して汚れを浮かせます。
その後、柔らかいクロスで優しく拭い、最後に大量の水で徹底的にすすぎます。
ここが重要なのですが、食器用洗剤には大きな「トレードオフ(代償)」があります。
それは、虫の油脂だけでなく、ボディに施工されているワックスや簡易コーティングも一緒に剥がしてしまう可能性が非常に高いことです。
食器用洗剤は、お皿の油汚れを落とすために強力な脱脂能力を持っていますからね。
虫汚れは落とせても、同時に塗装の保護膜(ワックスなど)を犠牲にする覚悟が必要です。
使用は広範囲でなく、虫が付着しているスポット的な使用に留め、洗浄後は必ずワックスやコーティング剤で塗装を再保護することをおすすめします。
これを怠ると、塗装が「すっぴん」の無防備な状態になり、紫外線や酸性雨のダメージを直接受けてしまいますよ。
重曹は塗装を傷つける?

お掃除の万能アイテムとして知られ、環境にも優しいイメージのある「重曹(ベーキングソーダ)」ですが、車のボディ(塗装)への使用は絶対にNGです!
「重曹は塗装を傷つける?」という検索をしている時点で、すでに危険なラインです。
答えは、「はい、100%傷つけます」と断言できます。
なぜかというと、重曹(炭酸水素ナトリウム)は、水に溶け残りやすい細かい「結晶」だからです。この溶け残った結晶が、非常に硬い「研磨剤(コンパウンド)」として作用します。
考えてみてください。重曹が掃除で活躍するのは、キッチンのシンク(ステンレス)や五徳の焦げ付き(ホーロー)といった、「非常に硬い素材」の表面を「削って」汚れを落とすからです。
しかし、車の塗装はそれらとは比べ物にならないほど「柔らかい」樹脂の膜です。
重曹 = 細かいサンドペーパー(紙やすり)
重曹を水に溶かしてペースト状にし、それでボディを擦る行為は、細かいサンドペーパーやキッチン用のクレンザーでボディをゴシゴシ擦るのとまったく同じ行為です。
車の塗装は、下地、色を塗るベースコート、そして一番表面を保護する「クリア層」という透明な樹脂の層でできています。
このクリア層が、紫外線や酸性雨からボディの色を守り、美しいツヤを出しているんです。
重曹で擦ると、この一番大事なクリア層に、無数の細かい傷(スクラッチ傷)が入ります。
その結果、太陽光が傷で乱反射し、塗装の命である「ツヤ」が完全に失われ、白くくすんだ状態になってしまいます。
一度こうなると、元に戻すには専門家による研磨(ポリッシング)しかありません。
インターネット上には「フロントガラスの浅い傷消しに重曹が使える」といった情報が存在する場合がありますが、それはまさに重曹が「研磨剤」であることの何よりの証拠です。
ガラスでさえ傷が入るリスクがあるものを、それより遥かに柔らかい塗装面に使うなんて、自殺行為でしかありません。
アルコールや漂白剤もNG
汚れ落としの最終兵器のように思えるかもしれない、「アルコール」や「漂白剤」。
これらも、塗装にとっては最悪の選択です。絶対にNGです。
アルコール(消毒用エタノール、IPAなど)
コロナ禍以降、消毒用エタノールなどが身近になりましたが、これも車には危険です。
アルコールは強力な「有機溶剤」です。
「有機溶剤」とは、簡単に言えば「油(有機物)を溶かす性質」がある液体です。
そして、車の塗装も「有機物(樹脂)」です。
「似たもの(有機物)は似たもの(有機溶剤)に溶ける」という化学の原則通り、アルコールは塗装のクリア層を文字通り「溶かして」しまいます。
高濃度のアルコールで塗装を拭くと、塗装が溶けてネバネバになったり、拭き取ったクロスの跡がそのまま塗装に転写されてしまったりします。
特に再塗装された車などは、非常に弱いので一発でダメになることも。
さらに危険なのが、バンパーやワイパーの根元(カウルトップ)、窓枠のモールといった「黒い未塗装樹脂パーツ」への付着です。
これらの樹脂パーツは有機溶剤に非常に弱く、付着すると部品内部の油分や可塑剤が溶け出してしまい、表面が白くカサカサになる「白化(はっか)」現象を起こします。
この「白化」は、一度起きたら交換以外に修復する方法がほぼありません。本当に取り返しがつかないんですよ。
塩素系漂白剤(キッチンハイターなど)
「シミ」を落とすというイメージから漂白剤を連想するかもしれませんが、これは論外中の論外です。
キッチンハイターなどの塩素系漂白剤は「強アルカリ性」の液体です。pH(ペーハー)でいうと12以上あったりします。
中性がpH7ですから、とんでもなくアルカリ性に振り切れていますよね。
車の塗装や、その上に施工されているコーティング被膜は、基本的に「中性」付近(弱酸性〜弱アルカリ性)の環境を想定して設計されています。
こんな強アルカリ性の薬品が付着したらどうなるか。
漂白剤が引き起こすダメージ
- ワックスやコーティング被膜は、瞬時に化学分解され、剥離します。
- 塗装自体も化学反応を起こし、変色したり、深刻なシミになったりするリスクがあります。
- 窓枠のゴム部品(ウェザーストリップ)や樹脂パーツに付着すると、深刻な劣化や変色(白化)を引き起こし、二度と元には戻らなくなります。
言うまでもありませんが、アセトン(除光液の主成分)やシンナー、ベンジンといった他の強力な溶剤も、アルコールと同様の理由で絶対にNGです。
激落ちくんの使用は絶対ダメ
キッチンのシンク磨きや茶渋落としなどで大活躍するメラミンスポンジ(「激落ちくん」などの商品名で知られていますね)。
れも、車の虫取りに使うのは絶対に、絶対にダメです!
「洗剤を使わずに水だけで落ちるから、エコで安全そう」なんて思っていたら、それはとんでもない勘違いです。
メラミンスポンジがなぜ水だけで汚れを落とせるか、その仕組みを知っていますか?
あれは、非常に硬い「メラミン樹脂」がミクロの単位で発泡した構造になっていて、その硬い樹脂の骨格で、汚れを「削り落として」いるんです。
つまり、メラミンスポンジ = 超強力な研磨剤(ヤスリ)なんです。
重曹が「細かいサンドペーパー」なら、メラミンスポンジは「もっと目の粗いサンドペーパー」や「金たわし」に近いかもしれません。
もちろん、陶器の茶渋やホーローのシンクなど、スポンジより硬い素材の汚れを「削る」のには最適です。
しかし、相手は柔らかい塗装(樹脂)です。
これはスポンジではなく、「ヤスリ」です。
メラミンスポンジで車のボディを擦るということは、虫の死骸ごと、塗装のクリア層をガリガリと削り落としているのと同じです。
虫は取れるかもしれませんが、その部分のクリア層は剥がれ落ち、深い傷だらけになります。
ツヤが失われるどころか、場合によっては下地の色が出てきてしまうかもしれません。
「ちょっとこびりついた虫に、角で軽く擦るだけなら…」という軽い気持ちが、愛車に致命傷を与えます。
このダメージを修復するには、専門家による高度な「磨き(ポリッシング)」が必要になりますし、傷が深すぎればクリア層を削り切ってしまい、再塗装(数十万円コース)以外に手がなくなるリスクさえあります。
キッチンの常識を、デリケートな車の塗装に持ち込むのは絶対にやめましょう。
放置した汚れは家のもので落ちる?
ここまで、家にあるNGアイテムを紹介してきましたが、実はNGアイテムを使うことと同じくらい、あるいはそれ以上に最悪なのが、「虫汚れの放置」です。
「放置した汚れは家のもので落ちる?」という疑問。
これに対する答えも、「絶対に落ちません」です。
なぜなら、時間が経過した虫汚れは、もはや単なる「汚れ」ではないからです。
それは、塗装が「損傷」した「跡」です。
このメカニズムを詳しく見ていきましょう。
虫汚れの正体=化学熱傷(ケミカルバーン)
虫の死骸や体液には、私たちが思う以上に厄介なものが含まれています。
それは「酸性」の成分や、タンパク質を分解する「酵素」です。
これらが車の塗装(クリア層という樹脂)に付着すると、塗装の分子結合を破壊し、文字通り「腐食」「侵食」させていきます。塗装が化学的に溶かされてしまうんです。
この化学反応を、強力に促進させてしまうのが「熱」です。
「太陽熱」や「エンジン熱」によってボディが温められると、化学反応の速度は飛躍的に上がります。
特に夏場の炎天下、ボンネットの上なんて、目玉焼きが焼けるほどの高温になりますよね。
あそこは、虫の体液が塗装を溶かすための、最悪の「培養器」になってしまうんです。
ダメージの進行ステップ
虫汚れのダメージは、時間と共にこのように進行します。
- 第1段階:付着直後(当日中)
虫の死骸が塗装の上に「乗っている」だけの状態。まだ塗装へのダメージはありません。この段階なら、水洗いやお湯でふやかすだけで簡単に除去できます。 - 第2段階:乾燥・固着(数日後)
体液の水分が蒸発し、タンパク質や油脂がカピカピに乾燥して硬くこびりつき始めます。この段階でも、まだ塗装の「上」にあるので、お湯や専用クリーナーでふやかして溶かせば除去可能です。 - 第3段階:侵食・シミ化(1週間以上)
熱によって化学反応が加速し、虫の体液がクリア層を溶かし始めます。これが、洗っても取れない「シミ」(塗装が変質した跡)や「クレーター」(塗装が陥没した跡)の正体です。
「汚れ」と「シミ(跡)」は決定的に違います
- 汚れ:塗装の「上」に乗っているモノ。洗えば落ちる。
- シミ(跡):塗装「自体」が変質・陥没した「損傷」。洗っても元に戻らない。
第3段階まで進行して「シミ」や「クレーター」になってしまったら、それはもう塗装が「ケガ」をしたのと同じ状態です。
お湯や食器用洗剤といった「家にあるもの」では、絶対に元に戻りません。
この状態で、取れないからといって重曹やメラミンスポンジで擦るのは、ケガした傷口にヤスリをかけるようなもの。
ダメージをさらに悪化させるだけですよ。
車の虫取りを家にあるもので行う場合の正しい手順

さて、ここからは実践編です!「家にあるもの」を使うリスクは十分理解した上で、それでも「今すぐ、付着したばかりの汚れを応急処置したい!」という場合。
どうすれば安全にできるのか、その正しい手順と塗装を傷つけないための「鉄則」を紹介しますよ。
場所ごとの注意点も合わせてチェックしてくださいね。
傷をつけない洗い方のコツ
車の虫取り、いや、これはもう洗車全体の鉄則なんですが、一番大事なのは「ゴシゴシ擦らない」ことです。
なぜか?
カチカチに乾燥した虫の死骸や、ボディに付着した見えない砂埃を、タオルやスポンジで引きずってしまうからです。
これが塗装面に無数の細かい傷(洗車傷)をつける最大の原因なんですよ。
じゃあどうするか。正しいプロセスは、「ふやかす」→「(化学的に)分解する」→「流す」です。
物理的な力(擦る力)は最小限に、熱や化学の力で汚れを浮かせることが重要です。
Step 1. 予洗い(ふやかす準備)
いきなりスポンジで擦り始めてはいけません。
まずは高圧洗浄機、またはホースの強い水流(シャワーではなくストレート水流)で、ボディ全体の砂やホコリ、そして軽く付着した虫を「吹き飛ばし」ます。
虫が付着して当日中であれば、これだけで大半が落ちることもありますよ。
Step 2. 徹底的にふやかす(最重要)
予洗いで落ちない固着した虫には、ここで「お湯」の出番です。
60〜80℃のお湯を準備し、虫が付着している箇所にゆっくりと、たっぷりとかけ流します。
前述した「お湯湿布」が最強です。
お湯に浸したタオルや厚手のキッチンペーパーを、虫の上に3〜5分ほど置いてパックします。
乾燥しないよう、途中で追いお湯をかけるとさらに効果的。
これでカチカチのタンパク質をふやかします。
Step 3. 化学的に分解する(※食器用洗剤を使う場合)
汚れが十分にふやけたら、ここで化学の力を使います。
「中性」の食器用洗剤をバケツで数百倍に薄め、洗車スポンジで揉んでよーく泡立てます。
たっぷりの泡を作り、それを虫の箇所に乗せます。
擦るのではなく「乗せる」イメージです。
そして、すぐに擦らず、界面活性剤が油脂を分解するまで数分間放置します。
Step 4. 優しく拭う・流す
成分が浸透し、虫の死骸が十分に柔らかくなっていることを確認したら、力を一切入れず、水で濡らして固く絞った柔らかい「マイクロファイバークロス」で「撫でる」ように優しく拭い取ります。
スポンジでゴシゴシはNG!
スポンジは面で圧力がかかり、砂粒などを引きずりやすいです。
最後の拭い取りは、汚れを繊維の奥に取り込めるマイクロファイバークロスが最適です。
ここでの「ゴシゴシ」が、洗車傷の9割の原因だと心得てください。一度で取れなければ、Step 2とStep 3を焦らず繰り返します。
Step 5. 徹底的にすすぐ
虫が除去できたら、洗剤成分がボディの隙間やゴムパーツの間に残らないよう、大量の水で入念に洗い流します。
すすぎ残しは、新たなシミの原因になりますからね。
食器用洗剤を使った場合は、ワックスが落ちている可能性が高いので、この後必ずワックスや簡易コーティング剤で塗装を保護してください。
基本的な流れは、洗車方法(トヨタ公式サイト)で解説している「傷をつけない洗車」と同じで、とにかく「優しく」が基本ですよ。
フロントガラスの注意点
虫が真正面からぶつかるフロントガラス。ここも厄介なポイントですよね。
「ガラスは塗装(樹脂)よりも硬いから、アルコールやメラミンスポンジでも大丈夫じゃない?」と思うかもしれませんが、これもNGです。
まず、虫の死骸に含まれる「油脂」がガラスに付着すると、これがワイパーで引き伸ばされ、視界を妨げるギラギラした「油膜」の原因になります。これが夜間や雨の日の運転で本当に危ないんですよね。
重曹やメラミンスポンジで擦ると、ガラス自体に微細な傷をつけ、光を乱反射させたり、ワイパーのビビリ音の原因になったりします。
さらに重要な注意点があります。それは、ガラス用クリーナー使用時の注意点です。
ガラス用クリーナー使用時の注意点
ガラス専用の強力なクリーナー(油膜取りなど)を使う場合、それが窓枠のゴム(ウェザーストリップ)や、ワイパーの根元にある黒い樹脂パーツ(カウルトップ)に付着すると、それらを深刻に劣化させたり、白化させたりする危険性があります。
アルコールなども同様です。
フロントガラスの虫取りは、基本はボディと同じく「お湯でふやかす」のが安全です。中性洗剤も使えますが、油膜の原因になることもあるので、しっかりすすぐ必要があります。
もし、虫は取れたけど油膜が残ってしまった…という場合は、家にあるもので油膜取りを行う方法で、ガラス面だけをきっちりリセットするのがおすすめですよ。
樹脂パーツの虫取り方法

フロントグリルやバンパーの下部、サイドミラーの付け根など、黒い「未塗装樹脂」のパーツも虫がこびりつきやすい箇所です。ここ、白っぽくなりやすくてデリケートなんですよね。
これらの樹脂パーツは、塗装されているボディパネル以上に、化学薬品に弱いんです。
特にアルコールやシンナーなどの「有機溶剤」が付着すると、前述の通り一発で「白化」してしまい、元に戻らなくなります。
また、最近の車に多い「ピアノブラック」の光沢ある樹脂パーツ。
あれも傷がめちゃくちゃ目立ちます。重曹やメラミンスポンジなんてもってのほかです。
さらに特に注意が必要なのが、グリルの縁取りなどに使われる「メッキパーツ」です。
あの光沢のあるメッキ部品は、酸性・アルカリ性どちらの薬品にも非常に弱く、食器用洗剤(中性以外)や専用クリーナー(アルカリ性のものが多い)が付着すると、すぐにシミや変色、くすみを起こしやすいデリケートな素材です。
ですから、樹脂パーツやメッキ部分の虫取りは、以下の方法が最も安全です。
樹脂・メッキパーツの安全な虫取り手順
- お湯で徹底的にふやかす(お湯湿布が最適)。
- 水流で流す。
- それでも残る場合のみ、「中性」の食器用洗剤を薄めた泡を乗せ、優しく洗う。
- 洗剤成分が残らないよう、徹底的にすすぐ。
強いクリーナーや溶剤は絶対に避け、とにかく「ふやかす」ことを第一に考えて対処してくださいね。
シミになった場合の対処法
「家にあるもの(お湯や中性洗剤)を試したけど、虫の形の『跡』や『シミ』が残ってしまった…」という場合。
これは本当にショックですよね。でも、ここで焦って重曹やメラミンスポンジで擦ってはいけません。
それはダメージを広げるだけです。
前述の通り、それはもはや「汚れ」ではありません。
虫の酸性体液によって、塗装のクリア層がすでに「侵食された(溶けた)跡」です。
この段階になってしまうと、残念ながら「家にあるもの」での対処は不可能です。
洗剤やお湯では、溶けた塗装を元に戻すことはできません。
じゃあ、どうすればいいのか。ステップを踏んで対処しましょう。
対処法1:専用の「虫取りクリーナー」を使用する(推奨)
もし「家にあるもの」での対処に行き詰まったら、無理をせず、市販の「自動車専用品」に切り替えることを強く推奨します。
なぜ専用品が優れているかというと、家にあるもの(お湯=熱、中性洗剤=界面活性剤)とは、汚れへのアプローチが根本から異なるからです。
市販の専用クリーナーの多くは「アルカリ性」に調整されています。
これが、虫の死骸の「酸性」の体液を化学的に「中和」します。
さらに、「タンパク質分解成分」が含まれており、こびりついた死骸そのものを化学的に溶かして除去します。
これは、お湯や中性洗剤にはない、虫汚れに特化した機能です。
代表的な専用クリーナーの例
- KeePer技研「コーティング専門店の虫とりクリーナー」: プロショップが開発した製品。コーティング施工車にも安心して使用できるとされています。
- SurLuster(シュアラスター)「ゼロクリーナー」: コンパウンド(研磨剤)が入っていないため、塗装を傷つける心配なく手軽に使用できるとされています。泡タイプなので液だれしにくいのも特徴です。
ただし、これらの専用品(特にアルカリ性のもの)も、メッキパーツや樹脂パーツへの使用には注意が必要です。
使用方法をよく読んで、正しく使うことが大切ですよ。
対処法2:最終手段は専門家(洗車専門店、整備工場)に相談
専用の虫取りクリーナーを正しく使用しても、光の加減で見える「シミ」や「跡」が薄っすらと残る場合があります。
前述の通り、これは塗装が侵食された(溶けた)跡です。この状態になると、洗剤やクリーナーで回復させることは不可能です。
このダメージを消す(正確には「目立たなくする」)には、ボディ磨き用の専用コンパウンド(研磨剤)とポリッシャー(研磨機)を使い、塗装の表面(クリア層)をごくわずかに削り、侵食された凹みを平滑にする「磨き(ポリッシング)」という高度な作業が必要になります。
素人が市販のコンパウンドで下手に磨くと、塗装を削りすぎたり、磨きムラができて余計にひどくなったりするリスクが非常に高いです。
この段階になったら、無理をせず、信頼できる洗車専門店や整備工場に相談することを強く推奨します。
「このシミ、磨きで取れますか?」と一度見てもらうのが一番ですよ。
車 虫取り 家にあるもの以外の予防策
ここまで、厄介な虫汚れの「除去作業」について長々と解説してきましたが、正直なところ、一番の対策は…「こびりつかせないこと」です。
これが最強の対策であり、一番ラクな方法です。
虫が付着すること自体は、車を運転する以上避けられませんが、「こびりついて取れない」状態や、「シミになる」状態は防ぐことができます。
そのための具体的な予防策を2つ紹介しますね。
予防策1:ガラスコーティングやワックスを施工する
これが最も効果的かつ根本的な対策です。
塗装の表面に、硬いガラス質の被膜(ガラスコーティング)やワックスの油膜といった「保護層(犠牲被膜)」をあらかじめ作っておくんです。
この「犠牲被膜」がバリアとなり、虫の酸性体液が「直接塗装に触れる」のを防いでくれます。
万が一、虫の体液がシミを作ったとしても、それはコーティング被膜の上が溶けただけで、その下の塗装自体は守られている、というわけです(被膜の種類やダメージの深さにもよりますが)。
さらに、コーティングやワックスの副次的な効果として、表面がツルツルになる(滑水性・撥水性)ため、汚れ自体が固着しにくくなります。
万が一虫が付着しても、お湯や水洗いだけで「するっ」と簡単に除去できるようになるんです。あの面倒な虫取り作業が、驚くほどラクになりますよ。
専門業者に頼む本格的なものから、DIYで手軽に施工できるガラスコーティング剤まで様々あるので、ぜひ検討してみてください。
これは虫汚れだけでなく、鳥フンや紫外線、酸性雨など、あらゆるダメージから愛車を守るための「保険」のようなものです。
予防策2:走行後は「即時」洗い流す
もう一つの、そして最も重要な習慣がこれです。
虫汚れは「時間との勝負」です。
前述の通り、虫汚れのダメージは「熱」と「時間」で加速します。
夜間の高速道路を走行した後や、山道をドライブした後など、「あ、今日はいっぱい虫が付いたな」と分かっている時。
そんな時は、「疲れたから明日でいいや…」と放置するのが一番ダメです。
塗装が侵食されてシミになる前に、可能な限り「当日中」、遅くとも翌日の朝(太陽で熱せられる前)には洗い流す習慣をつけましょう。
この「即時リセット」の習慣さえあれば、たとえコーティングをしていなくても、お湯や水洗いだけで簡単に汚れが落ち、シミになるのを防ぐことができます。
これが、塗装をキレイに保つ最大の鍵となりますよ。
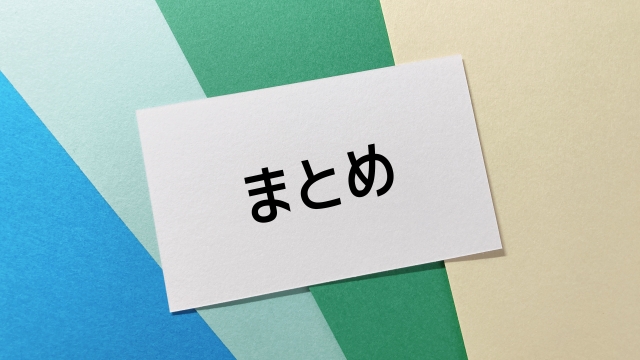
今回は、「車 虫取り 家にあるもの」というテーマで、安全な方法と絶対NGな方法を、その理由と共に徹底的に解説しました。
長くなりましたが、結論はシンプルです。
家にあるもので「付着直後」の応急処置ができるのは、「お湯(60〜80℃)」と「中性の食器用洗剤(ワックス落ちのリスク有り)」の2つだけです。
一方で、以下のアイテムは、塗装を回復不能なまでに破壊するリスクがあるため、絶対NGです。
| 絶対NGなアイテム | 理由(塗装への影響) |
|---|---|
| 重曹 | 強力な「研磨剤」。クリア層を傷だらけにし、ツヤを失わせる。 |
| メラミンスポンジ | 超強力な「研磨剤(ヤスリ)」。クリア層を削り取る。 |
| アルコール・シンナー | 「有機溶剤」。塗装(樹脂)を溶かす。樹脂パーツは白化する。 |
| 塩素系漂白剤 | 「強アルカリ性」。コーティングを剥離し、塗装やゴムを変質させる。 |
| (その他)酢、塩など | 酢は「酸性」で塗装を攻撃し、塩は「サビ」の原因となる。 |
虫汚れは「放置」すると、熱で化学反応が促進され、塗装を溶かす「シミ」や「クレーター」に進行します。
こうなると「家にあるもの」では対処不可能です。
無理に擦ってダメージを広げる前に、専用のクリーナーを使うか、専門家に相談してくださいね。
一番いいのは、コーティングなどで「予防」して、付いたら「即洗う」ことです。
愛車を長くキレイに保つために、正しい知識で対処していきましょう!
 smart-info
smart-info 


